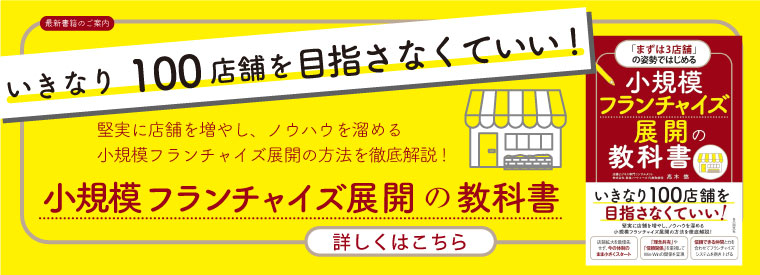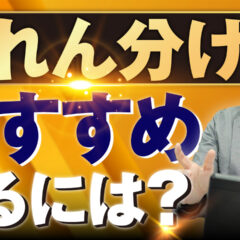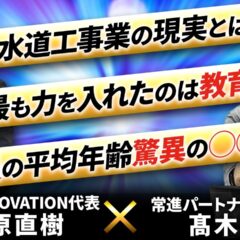前の記事「メニューブックをつくる①掲載商品を決める」では、クロスABC分析によって分類されたランク付けから掲載商品を決める方法を紹介しました。また、売上と粗利のランクだけでは判断できない選択の基準についてもお伝えしました。今回は、メニューブック掲載商品の価格の決め方について、そのポイントを紹介いたします。掲載商品の注文数を増やすには価格設定が大変重要な要素となり、店舗の売上・利益に大きく影響を及ぼすことになります。
価格はわかりやすくすること
価格設定がわかりやすくなると、顧客満足度を下げずに客単価が上がる傾向があります。信じ難い話に思われるかもしれませんが、商品の価格を全体的に値上げしたわけでもないのに、新しいメニューブックを使い始めると客単価が上がったお店がいくつもあります。これらのお店に共通することは、古いメニューブックの価格が整理されておらず、わかりにくいものになってしまっている点です。
お客様は注文をする前に、その日の予算をある程度決めており、それを超えないよう注文をセーブする傾向にあります。価格がわかりやすくなることで、合計金額が想定しやすく、予算との差額を把握しやすくなるため、予算金額になるまで注文を続けるようになります。その結果、客単価が上がるようになるのです。
ちなみに予算を考えるときは、「1,2,3,5」を意識するといわれています。つまり、1000円、1500円、2000円、3000円、5000円、1万円というきりのいい数字で予算を考えているお客様が多いといえますので、価格を考える際の参考にするとよいでそしょう。
価格を決める際に注意すること
メニューブック掲載商品の価格を決める際に注意することは以下の通りです。
同一カテゴリー内の商品は、価格ラインを少なくする
価格ラインとは、メニューブックに掲載されている価格の種類のことです。「焼き鳥」のカテゴリーで、180円・200円・230円・250円の4種類の商品があったら、「価格ラインは4つ」ということになります。
メニューブックの価格を決める際には、カテゴリーごとの価格ラインができるだけ少なくなるように注意します。価格ラインの数が少なければ少ないほど、お客様は価格を気にせずに、商品の内容や価値のみで好きなものを選べるようになるからです。同一価格商品が多くなることで、種類の豊富さを感じた上で、その中から気に入ったものを注文できるようになり、お客様の満足度は上がっていきます。
上限価格を決めた上で価格を決める
お客様の想定価格より高い商品があった場合、「この店は高い」という印象を持たれ、来店をやめたり、注文数が減ってしまったりすることが起きることがあります。そのため、上限価格を決めた上でそれを超えない価格を設定することが大切です。
ただし、上限価格よりどうしても高い商品がある場合には、3つの対応方法があります。
一つ目は、グランドメニューから外し、「本日のオススメ」などの差し込みメニューに掲載する方法です。
二つ目は、メニューブックに特別コーナーを設け、そこに掲載することで特別な商品であることをお客様に認知してもらう方法です。
三つ目は、値下げして上限価格を超えない価格にする方法です。
どの方法も一長一短ありますので、店舗の状況に応じて対応方法を考えることが大事です。
下限価格を引き上げる
下限価格を引き上げることによって、粗利の確保をすることができます。下限価格に近い安い価格については、お客様はあまり気にしていませんので、そのような商品の値上げをしても、クレームが発生することも、大幅に注文数が減ることもありません。ただし、メニューの全面リニューアル時など、他の商品も含めて全商品の価格を調整する場合に値上げすることが前提となります。
10円以下の桁を揃える
10円以下の桁を1種類か2種類にそろえることが大切です。「280円、580円」「330円、530円」のように80円と30円の2種類にそろえることです。2種類にそろえることで価格がわかりやすくなり合計金額が想定しやすくなるため、お客様のストレスを減らし、注文数を増やす効果があります。
以上、メニューブック掲載商品の価格の決め方について紹介してきました。メニュー価格の設定方法次第で、売上を上げることも利益を確保することもできます。ですから、十分に検討した上で価格を決めることが大切です。
無料メルマガ登録
専門コラムの他、各種ご案内をお届け中です。ぜひ、ご登録ください。

セミナーのご案内
店舗ビジネスの多店舗展開やのれん分け・FCシステム構築を進めていくため、具体的にどう取り組んでいけばいいのか、どのような点に留意すべきか等を分かりやすく解説する実務セミナーを開催しています。
セミナー一覧ぺージへ