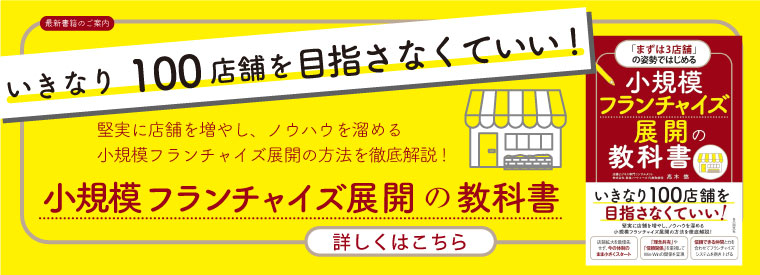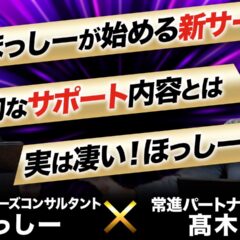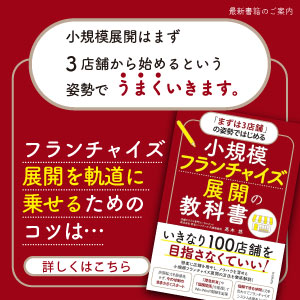(1)平均時給が過去最高を更新
株式会社リクルートジョブズが発表した2018年10月度の「アルバイト・パート募集時平均時給調査」によると、三大都市圏の10月度平均時給は前年同月より26円増加の1,047円になり、2006年1月の同社調査開始以来過去最高を更新しました。
今回首都圏の平均時給は1,089円で、前年同月より28円増加(増減率+2.6%)、前月比は10円増加(同+1.0%)し、職種別では、「販売・サービス系」「製造・物流・清掃系」(前年同月比増減額+31円、増減率+3.0%)、「事務系」(同+30円、+2.7%)、「フード系」(同+24円、+2.3%)など全職種で前年同月比プラスとなりました。
人手不足が深刻化していることは、厚生労働省が発表する求人倍率報道などに加えて、今回の調査結果からも伺うことができます。
経営資源の小さい中小企業にとって、給与など処遇の改善は難しいため、従業員にとって、「働きやすさ」や「働きがい」のある会社にして、従業員の離職率を下げる、もしくは、上げないようにするとともに、求職者にアピールすることが、人材確保に大切なことになっています。
なお、人手不足問題と「働きやすさ」「働きがい」のある会社について詳しく知りたい方はこちらのコラムをご覧ください。
(2)人事評価制度と評価エラー
従業員に長く働いてもらったり、求職者に「働きたい」と思ってもらうためには、従業員満足度を向上させる必要があります。
そのためには、アメリカの臨床心理学者ハーズバーグによれば、「満足」に関わる要因(動機付け要因)と「不満足」に関わる要因(衛生要因)があると言われています。
動機付け要因としては、「達成すること」「承認されること」「仕事そのもの」「責任」「昇進」などで、衛生要因としては、「会社の方針と管理方式」「監督」「給与」「対人関係」「作業条件」などです。
先ほどの調査結果の時給は、不満足を解消する衛生要因の一つになります。
給与を改善できたとしても、それだけで、人が満足して長く働き続けるわけではありません。
しかしながら、多くの企業において自社の働く場としての魅力を高めるために給与の高低にばかり着目している現状があるのは残念です。
人を動機付けるためには、「承認すること」が必要であり、そのために人事評価制度を活用します。
給与と異なり、承認することはコストがかからないため、経営資源の限られる中小規模企業こそ、積極的に仕組みとして取り入れるべきと言えます。
人事評価制度は、経営理念や経営方針を人事制度の内容と一貫性を持たせ、報酬や人員配置、人材育成につなげます。
しかし、人が行う評価には、評価エラーがつきものです。
そこで、どのような評価エラーがあるか把握し、自身の傾向をつかんだ上で、評価を行うようにすると、評価エラーが小さくなり、効果的です。
代表的な評価エラーには、以下のエラーがあると言われています。
表1 評価エラーの種類
| 種類 | 内容 | 主な対策 |
|---|---|---|
| ハロー効果 | ハローとは後光のことで、部下のある部分の評価ですべてを評価すること。具体的には、1つの面に優れていると、他の面においても優れていると評価すること。反対に劣った面ですべてを評価する場合もある。 |
|
| 寛大化効果 | 評価には、甘く、もしくは、厳しくなりがちだが、全般に甘くなる傾向。部下を高く評価したい気持ちや部下に嫌われたくない気持ち、部下の業務をよく把握していないことなどが背景にある。 |
|
| 厳格化効果 | 寛大化効果の逆。全般的に評価が厳しくなること。評価者の性格や管理職としての責任感、部下への個人的感情などが背景にある。 | |
| 中心化効果 | 評価が中心に偏ってしまい、優劣があるにもかかわらず、評価の差がでないこと。部下に嫌われたくない気持ちや部下の業務をよく把握しておらず、評価の自信がないことなどが背景にある。 |
|
| 対比誤差 | 会社の評価基準を用いず、評価者自身の基準で評価してしまうこと。評価者と似たタイプや好みのタイプの評価が高くなったり、もしくは、評価者の不得意の業務が得意な部下の評価が高くなる場合がある。 |
|
自分自身に思い当たる傾向はありましたか?
評価者の経験や性格などで、評価が甘くなったり、厳しくなったりしがちですが、評価エラーを極力小さくするためには、客観的な評価基準を用意すること、部下の業務をよく把握すること、評価者の訓練を行うことが、有効と言えます。
また、直属の上司である店長などの1次評価者や社長・役員クラスの2次評価者、人事部による評価などを設定し、必ず2段階以上の評価を行うことで、組織の仕組みとして評価エラーを減らす工夫ができます。
人事評価の大切なところは、評価が公正・客観的で、人や時期などによってブレないことですので、評価エラーをしっかり理解した上で、評価に臨みましょう。
(3)人事評価制度活用による効果
導入する人事評価制度は従業員から信頼される仕組みである必要があります。
それには、評価基準や処遇との関係をしっかり整理するなどの設計面と、評価者と部下が人事評価の仕組みを理解して公正な評価を行う運用面の両面が重要です。
評価エラーは誰でも起こしやすいものと理解し、自分自身の傾向を知ることで、従業員の正しい評価につなげ、従業員満足度を向上させましょう。
給与などの衛生要因ばかりではなく、従業員の成果を正しく承認することで、動機付け要因が高まります。
(コンサルタント・中小企業診断士 木下岳之)
無料メルマガ登録
専門コラムの他、各種ご案内をお届け中です。ぜひ、ご登録ください。

セミナーのご案内
店舗ビジネスの多店舗展開やのれん分け・FCシステム構築を進めていくため、具体的にどう取り組んでいけばいいのか、どのような点に留意すべきか等を分かりやすく解説する実務セミナーを開催しています。
セミナー一覧ぺージへ