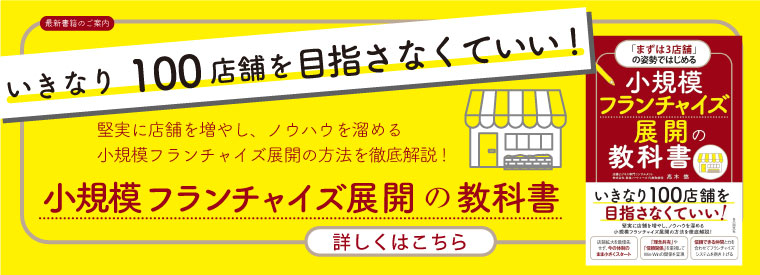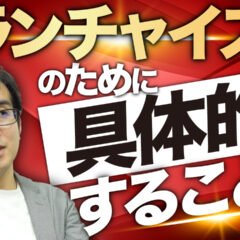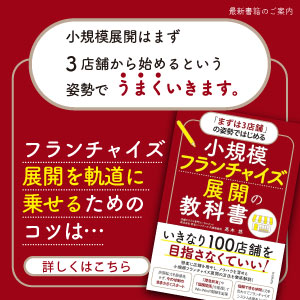こんにちは。
常進パートナーズの高木です。
弊社では、日々様々な企業で「のれん分け制度」導入のサポートをさせていただいております。
その中で、よく経営者に質問させていただくのことがあります。
それは、「将来、独立者にどのようになってほしいですか?」という質問です。
このように質問すると、多くの経営者は
「それはもちろん、のれん分けして経営者になってもらいたい」
とお答えになります。
ですが、私どもがお聞きしているのは、独立した後のその先の話です。
つまり、「のれん分けで独立した後、どのようになってほしいのか?」ということです。
この点は、本部、独立者双方にとって重要な内容になりますが、
意識をされていないことが多い印象を受けます。
そこで、今回は のれん分け制度を導入する経営者が考えておくべき「独立者の将来像」 をご紹介したいと思います。
なお、のれん分け制度構築についてさらに詳しく知りたい方は、こちらのコラムも合わせてご覧ください。
なぜ、「独立者の将来像」を決めておく必要があるのか
のれん分け制度を導入する経営者から見ると、制度導入後は「のれん分け制度を利用して独立してもらうこと」が当面の目標になるかもしれません。
しかし、ここで注意しなければならないことがあります。
それは、独立者から見ると「のれん分けで独立することは経営者としての第一歩に過ぎない」という点です。
創業経営者で「独立することが目標だった」なんて人あまりいないでしょう。
多くの場合、独立後に実現したい姿があったはずです。
仮に独立することが目標であったとするのであれば、そのような起業が上手くいく可能性は低いのではないでしょうか。
ですから、のれん分けにおいても、独立することにばかり目を向けるのではなく、「独立した後にどのような状態を目指すのか」という点を、本部、独立者双方が明確化しておかなければなりません。
のれん分け制度で目指すべき「独立者の将来像」とは
では、独立後のどのような状態を目指すべきなのでしょうか。
この点については、基本的には独立する経営者次第ですが、弊社では、本部のスタンスとして、
『3店舗以上を展開する経営者になること』
を推奨していくべきと考えています。
なぜかというと、独立者が3店舗以上展開することが、本部と独立者、双方に大きなメリットをもたらすからです。
以下、それぞれの視点から考えてみたいと思います。
独立者の視点
まず、独立者の視点で考えると、安定した経営を実現するために、複数店舗経営を目指していく必要があります。
創業経営者は、ご自身の経験を振り返ってみるとわかると思いますが、1店舗経営のときと、3店舗経営のときとでは、経営力に大きな差があるのです。
例えば、競合店が近くに出現したケースで考えてみましょう。
3店舗ある場合、競合店が近くにできて、1店舗の売上が低迷したとしても、残りの2店舗がある分、企業全体としての影響度は低下します。
一方、1店舗の場合には、競合店が近くに出来て売上が低迷すると、それがそのまま企業業績になるため、甚大な影響を及ぼします。
また、人材面で考えると、3店舗くらい経営していれば、余剰人員を抱えることができるため、急な離職への耐性をある程度持てますが、1店舗経営の場合、余剰人員を抱えることなど不可能です。
したがって、急な離職が生じたときには、一気に売上が落ちる、という事態が生じかねません。
このように、1店舗経営は、経営力という観点で見ると非常に脆弱な状態であり、独立者が安定的に経営をしていくためには、複数店舗経営を実現していく必要があるのです。
本部の視点
社員がのれん分け制度で独立した後、本部は様々なサポートを行い、独立者を成功に導かなければなりません。
のれん分けしたばかりの独立者は、資本も経験もないわけですから、特に丁寧にサポートをしていく必要があるでしょう。
当然、本部は多くの手間がかかります。
そこから、独立者が2店舗、3店舗と複数店舗展開をすすめていくなかで、資本と経験が蓄積し、本部によるサポートの必要性も低下していきます。
このような状態になって、本部にはじめてのれん分けしたメリットが生まれてくることでしょう。
この点、仮に独立者がずっと1店舗経営のままでいたとしたらどうでしょうか。
前述のとおり、1店舗経営の状態は、経営力が非常に脆弱です。
必然的に、本部は手間暇かけてサポートをしていかなければならなくなります。
1店舗経営者を3名抱えるのと、3店舗経営者を1名抱えるのとでは、店舗数自体は同じであったとしても、本部にかかる負担は全く異なるのです。
ですから、本部の負担を軽くしていくためにも、独立者には複数店舗経営を推奨していく必要があるのです。
まとめ
以上、今回はのれん分け制度を導入する経営者が考えておくべき「独立者の将来像」をご紹介しました。
このように、のれん分けで本部と独立者のWin-Winの関係性を実現するためには、独立者に3店舗経営者になってもらうことが極めて重要です。
のれん分け制度を安定的に運用していきたいと考えるのであれば、「のれん分けするまで」だけでなく「のれん分けした後」も見据えて制度設計をしておくことが大切でしょう。
無料資料ダウンロード
のれん分け・社員独立FC制度構築の手順やポイントをまとめた資料を無料進呈しています。宜しければ、下記よりダウンロードください。

セミナーのご案内
店舗ビジネスの多店舗展開やのれん分け・FCシステム構築を進めていくため、具体的にどう取り組んでいけばいいのか、どのような点に留意すべきか等を分かりやすく解説する実務セミナーを開催しています。
セミナー一覧ぺージへ