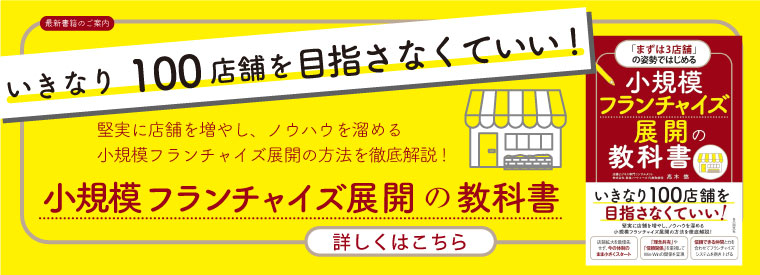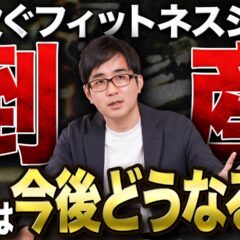ネットラジオ『多店舗化・フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所』は、弊社代表の高木と社労士の田村陽太が、飲食店、整体院、美容院等の様々な店舗ビジネスの「多店舗展開」を加速させるために重要な事を対談形式でお話しするラジオ番組です。
第80回 『なかなか社員に想いが伝わりません…。想いを共有していくためにはどうしたらいいでしょうか?』というテーマで店舗ビジネス専門コンサルタントの髙木悠が熱く語ります。
【ハイライト】
・『経営者と従業員は完全に別物と考えるべき』とは?
・従業員の価値観というフィルターを通過するためのコミュニケーションとは?
・従業員が興味があるのは「会社が〇〇」ではなく「自分が〇〇」論
・FC本部のSV(スーパーバイザー)として働く上で重要な事
・従業員との良好な関係構築が一番最強のフィルター通過策
・本当に嫌な従業員とのコミュニケーション手法とは?
多店舗化・フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所。この番組は株式会社常進パートナーズの提供でお送りいたします。
店舗ビジネス専門コンサルタントの高木悠が最速・最短で年商30億、店舗数30超を実現する実証されたノウハウをコンセプトにのれん分け制度構築、FC本部立ち上げ、立て直し、人事評価制度の整備など飲食店、整体院、美容院などの様々なビジネスの多店舗展開を加速させるために重要なことを対談形式で分かりやすくお話しする番組です。
田村:こんにちは。パーソナリティーの田村陽太です。配信第80回目となりました。本番組のメインパーソナリティーをご紹介します。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木悠さんです。よろしくお願いします。
高木:よろしくお願いいたします。
田村:高木さん、今日も質問頑張っていきましょう。
高木:お願いします。
田村:本日のテーマはこちらとなっております。「なかなか社員に想いが伝わりません。思いを共有していくためにはどうしたらいいでしょうか?」ということなんですけど、これは非常に重そうな質問なんですけども、いかがですか。
高木:これは大変ですよね、なかなか難しいですよね。
田村:はい。これ想いっていうのは社長自身がいつも喋っている想いみたいな感じで、どんな想いなんですかね。
高木:社員にこういう風になってほしいとかこういう風に動いて欲しいとか、そういう想いなんじゃないですかね。
田村:この想いの漢字が、「木に目に心」ですもんね。すごい気持ちがあるでしょうね、想いが。何かありますでしょうか?
高木:私よく経営者にお話するんですけど、経営者と社員の方っていうのは、基本的にもう全然別次元の人だと思うんですよ。
田村:それはズバリですね。それは何でしょう?
高木:いやあ、経営者って会社経営にすごいリスクを負っているじゃないですか。会社の経営がうまくいかなくなったら、それこそ自分で全部責任を取らなきゃいけないですよね。だから自分の財産とかも全て失うリスクもあるじゃないですか。
田村;そうですね。
高木:だから当然会社経営に対して本気ですよね。でも社員の方って、そうじゃないじゃないですか。当然会社で何かあったらそこで働くことはできなくなっちゃうんですけど、転職して他の会社で働けばいいわけですよね。
田村:はい。
高木:だから負っているリスクって全然違うじゃないですか。だから、私なりの言葉で表現すると、持っている「フィルター」が全然違うと思うんですよね。
田村:フィルター?
高木:コミュニケーションって、例えば話をするじゃないですか。社長が何か物事を発しました。でもその言葉がそのまんま相手に受け取られるのかっていうとそうではなくて、必ず相手の中にあるフィルターで変換されるわけですよね。
田村:価値観みたいなものですね。
高木:そうそう。変換されて、解釈されて、反応が出てくるわけじゃないですか。だからコミュニケーションするときに僕が大切にした方がいいなと思っているのは相手のフィルターを理解しておかなきゃいけないというわけですよ。
田村:なるほど。
高木:当然その経営者と従業員さんの間でコミュニケーションのフィルターが全然違うものがついているわけですね。だから社長から言ったら、会社のために一生懸命働くのは当たり前だと思っているわけじゃないですか。そういうフィルターが付いているわけですよ。
田村:はい。
高木:だから、ちゃんと働いていなかったら、それに対して怒るわけじゃないですか。でも、社員の方についているフィルターはもしかしたら「やってもやんなくてもそんなに給料変わらないんだったら、それはやりませんよね」っていうフィルターが付いてるかもしれないじゃないですか。
田村:なるほど。
高木:そうですよね。そこに対して「いや、何でもっと一生懸命やんないんだ」とかって言われても、彼のフィルターで変換されるから「うるさいことを言っているな」みたいになっちゃったりする可能性があるわけですよ。
田村:はい。
高木:だから、注意しなければいけないのは相手のフィルターをちゃんと理解して、そのフィルターを通過するような言葉を投げかけないと駄目ですよね。そこを意識してコミュニケーションとっていくと、だいぶ変わるんじゃないですかね。
田村:例えば相手のフィルターに通過できるような喋り方っていうのはどのようにしたらいいでしょうか?
高木:だから社員の方っていうのが何を大切にしているかだと思うんですよ。これはもう全然人によって違うじゃないですか。だから人によって言い方って変えていかなきゃいけないんですけど、まず必ず言えることっていうのは、社員が大切にしているものは何かって言ったら、「会社の経営」ではないんですよね。
田村;なるほど。
高木:会社の経営よりも自分の事の方が絶対に大切なんですよ。でも社長は会社の経営と自分のことが同じぐらい大切なんですよね。それは負っているリスクが違うからそういうもんだって思うしかないと思うんですよ。社員は会社のことよりも自分のことが大切じゃないですか。
田村;はい。
高木:ということは、少なくとも社長が発するメッセージは、会社のためにこうしなければならないっていう言い方をしていると、それは間違いなく相手のフィルターで止まるんですね。なので、その時に話す言葉としては、「こういう風にすることがあなたにとってプラスなんだ」っていう言い方ですね。
田村:はい。
高木:という言い方に変えていった場合、フィルターを通る可能性が上がるわけじゃないですか。ここを注意しなければいけないですね。
田村:確かに言いかえというか、自分の気持ちで発しようとしちゃうと、どうしても自分が主語になっちゃいますけど、相手を主語にするっていうのはやっぱり意識しないと駄目ですよね。
高木:そうそう。だからよくあるので言うと、売上を上げようみたいな話ってある訳じゃないですか。こういう目標にしようみたいなお話。これをそのまんま「この売り上げを目指そう!」って社長が言うじゃないですか。それは従業員さんのフィルターで止まるわけですよ。
田村:はい。
高木:従業員さんの興味があるのは会社の売上ではないんです。自分がどうなるかってことじゃないですか。だからそれを変換しなきゃいけないですよね。この売上目標をやることによって、あなたにどんな得があるとか、メリットがあるとか、幸せがあるのかっていう話をしないといけないじゃないですか。
田村:なるほど。
高木:そういうことをやったら給料も上がるかもしれないし。売上が上がるってことは良いサービスを提供できたりするわけじゃないですか。お客様の感謝とか得られる可能性もあるわけじゃないですか。
田村:はい。
高木:そうすると、その人の要は存在価値みたいなものが高まるっていうこともあるじゃないですか。だからそこに対して仕事のやりがいが感じられるようになることなのかもしれないし、給料が上がった結果家族がみんな幸せになれるかもしれないじゃないですか。
田村:はい。
高木:そこの言い方っていうのはいろいろあるんだと思うんですけど、要は相手にとってプラス、相手が目指している幸せみたいなものを実現できるんですよっていう言い方ですよね。その方が思いは伝わる可能性は高いですよね。
田村:確かにフィルターを通る確率高まりますよね。ありがとうございます。ちょっと1個質問したいんですけど、いろんな従業員さん価値観を持っているっていうお話があったじゃないですか。例えば売上一つ上げるにしても、この従業員さんにはこういう風な説明した方がいいとか、この従業員さんには給料が上がるから売り上げを上げようみたいな、そんな感じで話し方も変えるべきなんですかね。
高木:そうそう。だから基本的な考え方や話し方っていうのは持っていていいと思うんですよ。だけど、当然その人によって大切な事っていうのは全然違うわけじゃないですか。例えば、子供がいない人と子供がいる人では価値観って全然違うと思うんですよ。
田村:はい。
高木:だからその人が本当に大切にしているものとか目指しているものっていうのは何なのかっていうのをちゃんと捉えた上で、それに合った話し方っていうのはやっぱりしなきゃいけないんですよね。
田村:なるほど。
高木:何で僕がこんなことを言うかっていうと、私がスーパーバイザーという仕事をしているときに、結局コミュニケーションの一つで加盟店のオーナーから期待通りの反応を引き起こすっていうことが仕事だったわけですよ。
田村:はい。
高木:命令も何もできないわけですから、もうひたすら相手がどういう価値観を持っているのかっていうのをずっと見ているわけですよ。そのフィルターを通過するだろう言葉をやっぱり選んで投げるんですよね。超大変なわけじゃないですか、これって。
田村:すごい占い師みたいなことやっていますね(笑)
高木:いやいや(笑)だけど、コミュニケーションってそういうものだと思うんですよ。ただ話してればいいって話じゃなくて、相手が何を大切にしているのかっていうのはちゃんと知って、そこに対してこちらも語りかけていかないと、それは期待通りに動いてくれないですよね。だから、当然何の準備もしないでできることじゃないんです。
田村:はい。
高木:だから、例えば私がスーパーバイザーのときには、どういう話をするのかっていうのは当たり前なんですけど準備していますし、1回でそれってうまくいかないわけですよ。だから1回話してみた結果、想定してない反応があったとか、そういうのはちゃんとメモしておいて次に備えるんですよ。
田村:すごい。そんなのをやっていたんですね。
高木:そう。これがでも、やっぱりある種スーパーバイザーといったらコミュニケーションのプロなわけじゃないですか。
田村;そうですね。
高木:今日はこういう感じで話していくとかね。こういう話をすると、相手はこういうことを言ってくるであろうとかも想定できるんですよね。だから、それをいつもやれという話じゃないんですけど、例えば大切な話、半年に1回面談するとかもあるわけじゃないですか。
田村:はい。
高木:そういうときは少なくとも手ぶらで行ったら危ないですよね。
田村:駄目ですか、やっぱり(笑)
高木:それは危ないですよ。いやだって、山登りと言ったって、富士山とかのてっぺんまで行くのに、Tシャツとかで行きますか?っていう話じゃないですか(笑)
田村:死んじゃいますね、8合目ぐらいでね(笑)
高木:そうですよね。何も考えないで普通行かないじゃないですか。ちゃんと事前に準備しますよね。だからもしかしたら、相手のことを全然知らないのかもしれないですよね。
田村:格言ですね、それは。
高木:それは本当にあって、例えば僕がスーパーバイザーだった時でもそうなんですけど、人と人との関係をすごく求めている方とかがいて、例えばその人の子供の話とかを私がした後に、仕事の話をすると全然態度が変わる人とかがいたんですよ。
田村:そうなんですか。
高木:そう。その人はだから家族を大切にしていて、子供の話とかに共感してくれる人の事を求めているわけですね。僕はまず仕事の話は一旦置いておいて、そういう話でその人とまず人と人との関係性を作るわけじゃないですか。
田村:はい。
高木:そこからある程度落ち着いたら、仕事の話をちょこちょこっとするみたいなコミュニケーション手法にするだけで、その人が気持ちよく動いてくれるみたいなこともあるんですよね。でもそれは子供がいるとか子供のことをすごく大切にしているとか、そういうことがわからないと、そういうコミュニケーションにならないじゃないですか。
田村:そうですね。
高木:それはやっぱり情報を取っていかないと難しいですよね。
田村:なるほど。なんか今話聞いていて思ったんですけど、コミュニケーションもすごい大事なんですけど、コミュニケーションはやっぱり一朝一夕にはうまくいかないというか、ちゃんとそういう苦労や積み重ねというか、失敗を繰り返して上手くなっていくもんだなっていうのが分かりましたね。
高木:原則は相手が何を大切にしているのかや、どんな人なのかっていうのを興味持って、いろいろ話を聞いて、この人のフィルターってこういうところにあるのだみたいな所を掴めばいいんですよね。
田村;はい。
高木:それをわからずしてコミュニケーションって難しいですし、ましてや、経営者相手に自分が思っている期待通りの行動をしてほしいわけじゃないですか。
田村:そうですね。
高木:そういう事ですよね。となったら、それはもう相手のことを知らないと無理ですよね。そこが本当に原理原則です。相手の立場に立って、投げかけていく。そういうことをしてこの話をすると、スタートに戻ってくるんですけど結局関係性ができていくんですよ。
田村:なるほど。
高木:経営者と従業員さんとの関係性ができているじゃないですか。実はその関係性っていうのが一番大きいフィルターになりやすいんですよね。
田村:はい。と言いますと?
高木:と言うのは、社長と従業員さんの関係性が悪いと、どんなにコミュニケーションの技術を駆使しても、このフィルターで100%弾かれるんですよ。だから言い方を工夫しても無理なんですよね、関係性ができてないと。
田村:はい。
高木:だけど、関係性ができていると、もうそのフィルターはめちゃくちゃ大きい穴が開いていて、どんなのを投げてもそのまま入っていくんですよ。そういう経験ってありますよね。
信頼関係があるから、この人が言っていることだったらやろうみたいな状況になるじゃないですか。
田村:そうですね。ありますね。
高木:その状態が最強なんですよね。その状態を作るためには、やっぱり相手の事を知るのが大事です。もう本当のコミュニケーションを深めていくことで関係が整備できるじゃないですか。
田村;そうですね。
高木:おのずと、そういう相手がどういうことを大切しているんだとかっていうのを考えながら会話をしてたら、だんだん思いは伝わるようになっていくっていう話ですよね。
田村:そういうのがシンパシーと伝わってきますもんね。従業員さんにも「この人、なんか波長が合うな」ってなったら、この人の話を聞こうとか社長の思いについていこうみたいになっていきますもんね。
高木:そうそう。あとはそういう前提さえあれば、あとはもう社長の情熱ですよ。この人は本気だって伝わり、そこに信頼関係があれば、これは間違いなく相手には響くんですね。その状態をどう作るかっていう話じゃないですか。
田村:ありがとうございます。ちょっと時間が近づいてきたんですけれども、最後にもう1個だけ質問させてください。想いを伝えるためにはコミュニケーションが大事ってことがすごくわかったんですけども、とはいえですよ、やっぱり人間じゃないですか。
高木:はい。
田村:やっぱり好きな人もいれば、もうちょっと本当嫌いみたいな人いるじゃないですか。どうしても合わないみたいな嫌いな人がいると思うんですけど、そういう人の時の思いを伝えるための対処策というのが一つの質問です。
高木:はい。
田村:また、それを今までの高木さんの社会人経験でどんな風にして克服してきたかのような、そういうワンポイントアドバイスを教えてください。
高木:何で苦手かなんですけど、私の経験則でいくと、苦手だと思っているその原因は相手のことをあまり知らないからっていうところです。勝手になんかそういう風に決めつけていって、その結果コミュニケーションも深まらないという事です。当然苦手だなって思っている人をどうこう話したいって思う人はいないじゃないですか。
田村:そうですね。
高木:でも田村さんもそういう経験ありませんか。こういう人と思っていたけど、話していたら全然違うみたいな。
田村:ありますね。すごいなんかとっつきにくい感じかなと思ったら、意外と喋ってみたらいいところあるなみたいな。意外と優しいところもあるのだみたいなのはありますね。
高木:そうそう。特に経営者と社員っていう関係だとすると、それはもう関わらないでいいっていう状況にはできないじゃないですか。関わらないでいいじゃんという風に思っちゃうと、むしろ会社は悪い方向にいっちゃうと思うんですよね。
田村:はい。
高木:だからもうそこって避けて通れないんだから、まずはだから相手のことをちゃんと知りましょうというお話ですよね。だからもう苦手だし、なかなかいうことも聞いてくれないんだけど、仕事のことを一旦置いといて、どんな人なのかなっていうところが肝心じゃないですか。
田村:そうですね。
高木:そういうところから入っていけば、僕の経験だと、なかなか言うこと聞かない人とか、いわゆる手間がかかる方であればあるほど、そういう仕事以外の部分で話を深めると、一発で変わるみたいなことって多いですよね。こんな人なんだ!みたいな。
田村:さっきの子供が好きとか、釣りが好きみたいな事ですか。
高木:そう。そういうところで共通点を見つけて共感が生まれたりね。実はなんかいやな人だと思っていたけど、こんないいところがあるんだみたいな所を見つけたりして、そういうお話をこちらが受け入れたり、承認をしたりするだけで、全然お互いの関係が変わるわけじゃないですか。
田村:はい。
高木:苦手だなと思っていたら、実はこんな人だったんだなってこっちも受け入れているわけじゃないですか。結構変わりますよねっていう話です。
田村:そうですね。ありがとうございます。想いを伝えるためには、なんか一方通行なイメージがありましたけど、相手のことをまず知る等双方向のことが大事なんだなってすごく思いました。本日は、社員に想いを共有していくためには何が必要かについてお話いただきました。ありがとうございました。
高木:ありがとうございました。
無料メルマガ登録
専門コラムの他、各種ご案内をお届け中です。ぜひ、ご登録ください。

セミナーのご案内
店舗ビジネスの多店舗展開やのれん分け・FCシステム構築を進めていくため、具体的にどう取り組んでいけばいいのか、どのような点に留意すべきか等を分かりやすく解説する実務セミナーを開催しています。
セミナー一覧ぺージへ