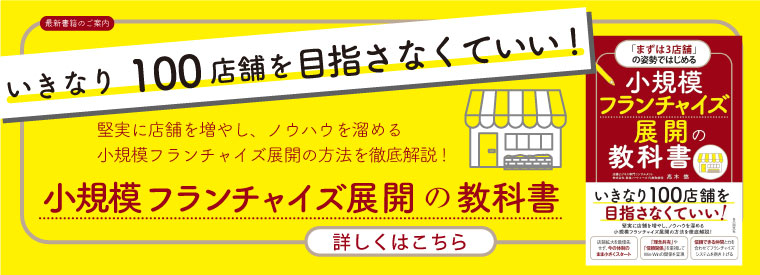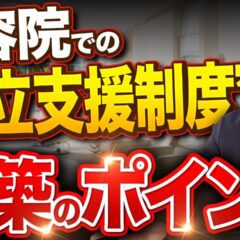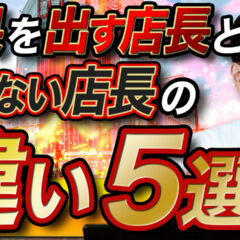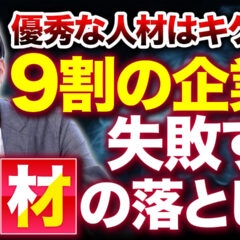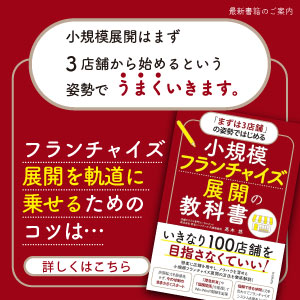ネットラジオ『多店舗化・フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所』は、弊社代表の高木と社労士の田村陽太が、飲食店、整体院、美容院等の様々な店舗ビジネスの「多店舗展開」を加速させるために重要な事を対談形式でお話しするラジオ番組です。
第23回『整骨院を経営しています。院長教育で悩んでいます。教育のポイントについて教えてください。』というテーマで店舗ビジネス専門コンサルタントの髙木悠が熱く語ります。
【ハイライト】
・店舗責任者教育で苦労する事
・院長教育が良ければ売上に直結する理由
・店舗責任者を人選する際のポイント
・問題解決能力の育成方法
・結果ではなく行動をコントロールする重要性
・教育には二種類ある?
多店舗化・フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所。この番組は株式会社常進パートナーズの提供でお送りいたします。
店舗ビジネス専門コンサルタントの高木悠が最速・最短で年商30億、店舗数30超を実現する実証されたノウハウをコンセプトにのれん分け制度構築、FC本部立ち上げ、立て直し、人事評価制度の整備など飲食店、整体院、美容院などの様々なビジネスの多店舗展開を加速させるために重要なことを対談形式で分かりやすくお話しする番組です。
田村:こんにちは。パーソナリティーの田村陽太です。配信第23回目となりました。本番組のメインパーソナリティーをご紹介します。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木悠さんです。よろしくお願いします。
高木:よろしくお願いします。
田村:高木さん、今日も頑張っていきたいと思うんですけど、今日の質問はこちらとなっております。「整骨院を経営しています。院長教育で悩んでおります。教育のポイントについて教えてください。」ということなんですけど。院長教育っていうのがあるんですね。
高木:整骨院なんで、院長なのでしょうけど、飲食店で言ったら店長教育とか店舗の責任者の教育についてですよね。これはなかなか難しい問題ですし、私は仕事でいろんな経営者さんと関わりますけど、みんな悩んでる問題ですよね。
田村:そうなんですか。どういうところが悩んでるんですか。
高木:やっぱり店舗責任者の能力とか姿勢次第で店舗の売上ってやっぱり全然変わってしまうわけですよ。私がマネージャーやったときにも優秀な店長を異動させると、3ヶ月ぐらいで売上が2,30%下がるとかもしくは上がるとか、やっぱり平気であるんですよね。
田村:そうなんですか。
高木:だけど、こういうことをやったら優秀な店舗責任者になりますよって簡単に教えられるような内容じゃないということですよね。なかなか属人的な部分もあって、そこがすごい難しいポイントにはなるのかなと思うんですけどね。
田村:一つ質問したいんですけど、その店舗責任者の力量によって売上が上下するっていうのはどういうことでそうなるんですか。何が影響するんですか。
高木:例えば私が働いてた飲食店とかで言うと、料理が同じであったとしても、店舗で働くスタッフのやる気とか、あとは人間関係が良ければ店舗の雰囲気も良くなったりするわけじゃないですか。だからそういう状況によってお客さんの満足度も大きく変わるんですよね。
田村:はい。
高木:だからそういう雰囲気をしっかりと作れる店長っていうのはやっぱり優秀で、その店長が行くと売上上がると。だけど人間関係がボロボロになってしまったりだとかそもそも店長がスタッフから嫌われてるとか、そんな状態だと従業員も言うことを聞かないわけじゃないですか。
田村:そうですね。
高木:そういうことになってしまうと、やっぱりなかなか売上は伸びないですよね。
田村:なるほど。もう一つ質問したいんですけど、整骨院で言うと、例えば人間関係がよければ、売上に直結するって話してたじゃないですか。整骨院で人間関係を良くすると、どうやったメカニズムで売上が高まったり、上がっていったりするんですか。ちょっとイメージがつかなくて、すみません。
高木:そもそも人間関係がめちゃくちゃ悪いところと人間関係がいいところで働いてるときに、そのスタッフの表情ってどうなのかとか、嫌なところで働いてたらもう無表情でやるでしょうし。そんなモチベーション高くお客様のために頑張ろうという感じでやるかって言ったら、なかなかそうならないわけですよ。
田村:はい。
高木:だけど店舗の雰囲気ってのがすごく良くて、院長が「こういう目標を目指そう!」と言ってマネジメントできてたら、みんな生き生きと働くわけじゃないですか。どっちのお店に行きたいかって言ったら、それは後者なわけですよ。
田村:なるほど。それがやっぱりお客さんにとっても来やすいお店になっていくみたいな感じですね。
高木:そうそう。結局チェーン店って提供している商品とかサービス自体が違うかと言ったら違わないじゃないですか。同じなんですよね。だけどその店長が変わると、売上が2,30%変わったりするっていうのは、結局が働いてる人のモチベーションとか仕事に対する姿勢でしかないわけですよ。
田村:はい。
高木:だからそこを生み出せる、店舗責任者や店長とか院長っていうのはすごく優秀なわけですよ。だけど、結局その人によってやり方も変わってくるわけじゃないですか。
だから、やっぱり一概に「こうしたらいいよ」なんて言えないわけですよ。なのでめちゃくちゃ難しい。
田村:なるほど。もう一つ質問なんですけど、店舗責任者となるべき人間というのはどういうところで人選していくものなんですか。どういうところが大事なんですか。
高木:ここがやっぱりその教育のポイントになってくると思うんですけど、まずやり方、店舗のマネジメントの仕方っていうのはやっぱり店長とか院長のキャラクターとか性格があるじゃないですか。だから同じやり方をやったら必ずしも結果が出るっていうことはまずあり得ないわけですよ。
田村:はい。
高木:だから、その人に合ったマネジメントの仕方っていうのはやっぱりやっていかなければいけないわけじゃないですか。そのときに私がすごく大切だなって考えてることが、私は「問題解決能力」って読んでるんですけど、ちゃんとそれを身につけてもらうことです。
問題解決能力って何かと言ったら、要は目の前にうまくいかない出来事って何でもあるわけじゃないですか。いろんなことがあるわけじゃないですか。
田村:はい。
高木:うまくいかないことっていうのをちゃんとこう受けとめて、それを乗り越えていくために、私がとれる最善の手段とは何なのかっていうことをちゃんと考える事ですよね。これが大切だと思いますね。
田村:なるほど。そういう力が大事になってくるんですね、院長教育としても。それって例えばいろいろ店舗を任されていくと、お客さんによっていろんなトラブルだったり、いろんな案件が降ってくるじゃないですか。そういう解決能力っていうのは、どうやって身に着けていくものなんですか。
高木:これって、訓練していくしかないわけですよ。だから、そういった、問題をしっかりと受けとめて解決策を考える時間を会社が従業員に提供していくってことですね。
田村:といいますと、どういう事でしょうか?
高木:だから例えば、月に1回とか会をかするわけじゃないですか。よくある駄目なパターンは、今月の売上目標はこれですとそこだけ確認して終了みたいな話が駄目なパターンです。なんでかっていうと、店舗責任者は売上自体のコントロールができないんですよね。売上を1万円上げてくださいって言われたって、それはできないんですよ。確実にできる方法ってないじゃないですか。自分が1万円をそこに入れる以外に(笑)
田村:はい(笑)
高木:これをやったら1万円上がるっていう、絶対的に上げられる方法っていうのはまず間違いなく無いんですよ。だから結果ってコントロールできないんですけど、売上を1万円上げるための行動っていうのは、店舗責任者はコントロールできるわけじゃないですか。
田村:なるほど、自分自身の行動というか。
高木:そう。例えば1万円上げるために、「じゃあ僕はチラシを1日100枚まきます」とかね。それをやったら必ず売上1万円上がるかどうかわかんないんですけど、それをちゃんと考えるっていうところが、これは本当に大事です。
田村:はい。
高木:というのは、例えばその人のモチベーションを高めるっていう唯一最善の方法ってないわけですよ。相手もいろんな人がいるし、店舗責任者もいろんな人がいるわけじゃないですか。基本的にその解決手段ってわかんないわけですよ。
田村:はい。
高木:だけど、ちゃんと会議で「僕はスタッフのモチベーションを上げて売上を上げるために、これが問題だと思うから、具体的に僕はこういう行動をします」って、自分で考えて実践できる人、それで結果思い通りにいったのか、いかなかったのか。それはもうわかんないじゃないですか、やってみないと。
田村:そうですね。
高木:でもちゃんとそれを振り返って、また次の行動に繋げていけるっていう人は超優秀な店舗責任者じゃないですか。
田村:なるほど。もう1個質問したいんですけど、その店舗責任者の方が自分自身の行動を振り返る時間っていうのは、自分で作っていくものなんですか。それとも会社がそういうのを作っていくものなんですか。
高木:理想は店長とか院長が自分でそういう風なことができたら、これはもう超一流なわけですよ。だけどそんなほっといてもできるような人っていうのは多分100人いて1人いるかいないかだと思うんですね。
田村;結構少ないんですね。
高木:だからそういう考え方をやっぱり教えていかなきゃいけないですよね。これって経営者の方って、やっぱり結果はコントロールできないし、結果を変えるためには行動を変えなきゃいけないっていう、自分がリスクを負ってるからおのずとわかるわけですよ。だけど、従業員さんって、別にその結果に責任を負ってないじゃないですか。
田村:そうですね。
高木:売上がいかなくても、給料が半分にならないじゃないですか。だからやっぱりそういう考えになりにくいんですよ。売上がいかなかった時に、周りに悪影響があれば、近くに競合店出来たからと言い訳に目を向けてしまうわけですよ。だから、結果だけ目あててると意味がないんですよね。
田村:はい。
高木:なので、会社は「あなたの目標はこれです。これを達成するためにあなたは具体的に何をしますか。」という投げかけをして、でちゃんとそれを考えるよう言われたら考えざるを得ないじゃないですか。
田村:そうですね。
高木:「いや競合店がいたからできなかったんです。」とか店長とかが言ったら、「いや、だから競合店がいるとかはうちではコントロールできないから、そうじゃなくてあなたに何ができるんですか?」という話なわけですよ。というのをしつこく投げかけていって、結局その起きた問題を自分なりの行動でどうにか乗り越えるっていうマインドを見つけていく。これを私は問題解決能力って呼んでるんですよ。
田村:そういうことなんですね。もう1個質問したいんですけど、院長って僕のイメージだと、最初従業員さんとして入ってきて、本当に偉いマネジメント層みたいな感じに僕はイメージしてて、院長になる前に普通の従業員さんとしてそういう能力を教育していくよりかは、院長に会ったときにそういうのを教えていく方がいいんですか。
高木:そうですね。それはもうできるだけ早くやった方が良いですね。これって院長だけできればいいっていうお話ではなくて、例えば普通のスタッフでも、お客さんから何か怒られたというときに、決まりきった対応をしてたら炎上するわけじゃないですか。やっぱり臨機応変に対応しなきゃいけないわけですよ。
田村:はい。
高木:そうすると目の前に起きた問題に対して、私がとりうる最善の行動は何かって考えて行動できなきゃいけないじゃないですか。それができる人が一流になっていくわけですよ。だからやっぱり現場で働く人とか全社員に何をするのかという問題に対して、取るべき行動っていうのを自分で考えてもらうことはやっておいた方がいいですよね。
田村:早いうちからやった方がいいってことですね。
高木:私は教育って2種類あると思ってます。やり方を教える、つまり「レジはこうやって打つんだよ」みたいなやり方を教えれば済むものってあるわけじゃないですか。ルーティーンですね。そういう業務を教えることも教育じゃないですか。
田村:教育ですね。
高木:だけどただやり方を教えるだけじゃできないことってあるんですよね。それを私は「問題解決する業務」って呼んでるんですけど。
田村:それは答えがないという業務ですね。
高木:そう。ちゃんとその二つを教育していかなきゃいけない。階層が上がれば上がるほどのルーティーンの業務っていうのはやっぱり比重が少なくなっていって、正解のない業務が増えていくわけじゃないですか。だから院長はより一層そっちが重要になってくるっていう話です。
田村:なるほど。結構時間も近づいてきたんですけど、院長教育のポイントということで、リスナーさんの経営者が今からできること、自分たちでできることをちょっと教えていただければと思うんですけど。
高木:目標って店舗にあると思うんですよ。とか今起きている問題っていうのはやっぱり目の前にあるわけじゃないですか。だから月に1回でもいいんでそういったものをまず確認をする場を設けて、そこに対して院長が自分でその解決のため、もしくは目標達成のために具体的に何をするのかっていうことを考えてもらって、少なくてもいいんで三つぐらいちゃんと書いて、それを翌月にちゃんとやったかどうか、結局どうだったのかっていうのを振り返るような場を設けていく。これを繰り返していくだけで半年もしたらかなり力がついていくと思いますけどね。
田村:なるほど。そのときの社長の院長に対するフィードバックの仕方ってどんな風にしたらいいんですか。この店舗責任者はできたね、できなかったねっていう評価の仕方っていうか、それはどんな風にやったらいいですか。
高木:やっぱり社長は行動面にフォーカスを当ててあげてほしいなと思うんですよ。だからこの問題を解決するためにこういう行動をするって社長が院長に言うわけじゃないですか。
その行動をやったけど、問題が解決しなかったとか目標達成できなかったってことはあるわけですよ。
田村:ありますね、絶対。
高木:だけど私は別にそれって全然悪いことじゃないと思うんですよね。やっぱり正解がないし、やってみないとわかんないし。やってみてこのやり方じゃ駄目だったって学ぶのも教育っていうか、勉強になるわけじゃないですか。やってるのに結果いかなかったことを責められたらモチベーションが下がると思うんですよね。
田村:はい。
高木:だからちゃんとそういったやったことを認めてあげて、でも目標達成ができてなかったり、問題解決できてなかったとしたら、「駄目なのは駄目でしょうがないし、もうきちっとできたから、じゃあ次はこれを乗り越えるために何するんですか?」と、ブラッシュアップをしていくわけですよ。そうすると全然嫌な感じがしないですよね。
田村:はい、そうですね。行動もちょっと認められてますし。
高木:そうそう。それで、行動しなかったときだけ、やっぱりそこは厳しくしないといけないと思うんですよ。それは自分でコントロールできる話なので。
田村:そうですね。自分で振り返りもできますしね、それはね。社長さんが店舗責任者の方への聞き方っていうのは、「次何するの?」のように高木さんみたいな感じで聞いたら良いんですか?(笑)
高木:もっと優しくかな(笑)使い分け出来たらいいですよね。あんまり詰められたら萎縮しちゃうような方、そっちの方が多いでしょうね。特に、まだ経歴が浅いとかね。私なんかはもう明確にこれ使い分けてますけど。
田村:そうなんですか(笑)
高木:やっぱり経歴があんまりない社員の方とかには、かなり優しくといったら変ですけど「どうすんの?」とか「なんでやらなかったの?」とかそういう言い方は避けますよね。ただある程度能力が身に付いてくれば、それはもう本人自分でわかりますから、そこはやっぱり「じゃあ次どうすんの?」っていうプレッシャーをかけていくっていうのも、それはそれで必要なときっていうのがあるわけですよ。
田村:なるほど。店舗責任者の心のレベルやそういう技術的なレベルも上がってきたら、聞き方も変えていくみたいなのが大事なんですね。
高木:はい。
田村:なるほど。高木さん、今日は貴重なお話ありがとうございました。
高木:はい、ありがとうございました。
無料メルマガ登録
専門コラムの他、各種ご案内をお届け中です。ぜひ、ご登録ください。

セミナーのご案内
店舗ビジネスの多店舗展開やのれん分け・FCシステム構築を進めていくため、具体的にどう取り組んでいけばいいのか、どのような点に留意すべきか等を分かりやすく解説する実務セミナーを開催しています。
セミナー一覧ぺージへ