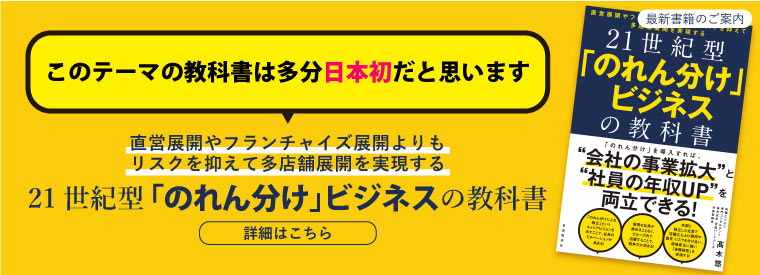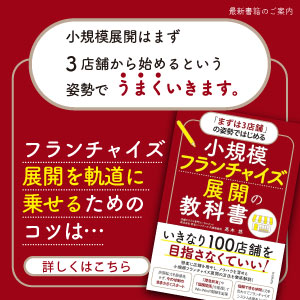ネットラジオ『多店舗化・フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所』は、弊社代表の高木と社労士の田村陽太が、飲食店、整体院、美容院等の様々な店舗ビジネスの「多店舗展開」を加速させるために重要な事を対談形式でお話しするラジオ番組です。
第22回『現在飲食店を2店舗経営しています。これから多店舗展開を進めていくにあたり、何から取り組んだらよいでしょうか。』というテーマで店舗ビジネス専門コンサルタントの髙木悠が熱く語ります。
【ハイライト】
・多店舗展開を目指す経営者の不安
・経営理念とは『魂の叫び』
・暑苦しいHPにならないために
・経営計画を共有する際には〇〇が大事
・多店舗展開する上で一番重要な事
多店舗化・フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所。この番組は株式会社常進パートナーズの提供でお送りいたします。
店舗ビジネス専門コンサルタントの高木悠が最速・最短で年商30億、店舗数30超を実現する実証されたノウハウをコンセプトにのれん分け制度構築、FC本部立ち上げ、立て直し、人事評価制度の整備など飲食店、整体院、美容院などの様々なビジネスの多店舗展開を加速させるために重要なことを対談形式で分かりやすくお話しする番組です。
田村:こんにちは。パーソナリティーの田村陽太です。配信第22回目となりました。本番組のメインパーソナリティーをご紹介します。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木悠さんです。よろしくお願いします。
高木:よろしくお願いします。
田村:高木さん、今日も頑張っていきましょう。それでは今日の質問はこちらとなっております。「現在、飲食店を2店舗経営しています。これから多店舗展開を進めていくにあたり、何から取り組んだらよいのでしょうか。」という質問なんですけども、お答えください。
高木:一番大変な時期ですよね。だいたい2店舗から3店舗ぐらいっていうのが最初の壁とよく言われてます。これどういうことかっていうと、2店舗ぐらいだと、社長1人で割と見れるんですよね。要は半分半分ぐらいでお店に入れるじゃないですか。
だから2日にいっぺんぐらい店舗を見て、マネジメントしていれば状況はだいたい把握できるわけですよ。
田村:はい。
高木:それがやっぱり3店舗ぐらいになってくると、マックスで働いたって3分の1しか一店舗ずつに居れないわけですから、どうしたって目に見えない部分が出てくるんですね。
社長がスーパーマンだったら5店舗とか行けたりするんですけど(笑)
田村:はい(笑)
高木:なかなかそれって難しいじゃないですか。やっぱりそこって、その人のやっぱりスキルとかにもよると思うんですよ。だからやっぱ3店舗行くと、今までの課題が少し変わってきて、自分が店舗を見てなくても、自分がいた時と同じような店舗運営ができなければいけないですよね。そうすると、課題が人材育成とか仕組み作りに移っていく、ちょうどそれぐらいの規模感なんですね。
田村:経営者がやるんじゃなくて従業員に任せていくフェイズって事ですか。
高木;そうそう。それができないと、ここから先って展開できないんですよ。よく3,店舗ぐらいで展開が止まるっていうのは、そこですよね。従業員さんに任せたら運営品質が落ちるとか、そもそも任せようとしないで社長が全部やろうとして、回らなくなる感じなんですよ。だから人に任せていくために何をしなければいけないかっていう観点で考えていかなきゃいけないですね。
田村:なるほど。ちょっと質問なんですけど、この質問者の方も2店舗経営してて、これから店舗展開していきたいと。何から始めたらいいですかっていうことで、問題意識を抱えてるじゃないですか。問題意識を抱えるっていうのは、やっぱり限界を経営者の方が感じちゃうってことなんですかね。
高木:不安があるんじゃないですかね。自分が見れなくなる中で、ここから店舗を出していくと、何をしなければいけないのか。
田村:自分が店舗の中身を見れないから不安になるというのかみたいな感じですか。それが問題意識っていう事ですか。
高木:そうですね。
田村:なるほど。「何から始めたらいいのですか?」っていうこれからするべきステップの話なんですけれども、何から始めていったらいいんでしょうか?
高木:ですから、やっぱり従業員さんのモチベーションアップとか、教育っていうところに繋げていかなきゃいけないじゃないですか。だからその前提として絶対やらなければいけないことがあるんですよ。それは何かって言ったら、一言で言うと、会社の経営方針とか経営理念とかって言われるものを、ちゃんと明文化して、それを全従業員さんに対して、バシッとまず示すことですね。
田村;なるほど、それは具体的にどういう事でしょうか。
高木:というのは、従業員さんのモチベーションとかを上げていくっていう観点で考えたときに、会社が何を目指してるのかとか3年後5年後にどういう状態になっているのかみたいなことが見通せないと、そもそもその会社でずっと働いていたいと思わないですよね。
田村:そうですね。先が見えないというか、本当にこの会社についてっていいのかって不安に思っちゃう従業員さんもいるでしょうね。
高木:そう。だからやっぱり3店舗目出すとか、でも多分そういう会社はおそらく3店舗で止まらないと思うんですよ。5店舗10店舗とかを出す計画や思いがあると思うんで、そういう思いをまずビシっと示す。
田村:はい。
高木:それを実現するためには、会社として乗り越えなければいけない課題っていくつかあると思うんですよ。3店舗とか5店舗で展開していくと、経営者1人で店舗見きれなくなりますから、誰か統括店長みたいなものを育成していかなければいけないとかがあるじゃないですか。
田村:はい。
高木:それが課題なので、「ここをこれから取り組んでいきたいと思います」っていうところをちゃんと紙に落として従業員さんに共有し、一緒に頑張っていこうという。
田村;それが大事なんですね。会社の理念っていうのも大事ですし、会社がどうオペレートしていくかっていうところの実務的なところというのを具体的に落とし込んでいくという感じですね。
高木:そうですね。まずそれがないと始まらないですよね。
田村:なるほど。もう1個質問したいんですけど、僕の素人的な考えで質問をしたいんですけど、いろんな会社のホームページを見てると、経営理念ってどこの会社も書いてるじゃないですか。1.〇〇が大事、とか2.社会貢献とか、3〇〇とか、すごい綺麗な経営理念があって、本当にこの会社大丈夫かなって僕思っちゃうんですけど、経営理念の作り方というかポイントってどんな感じで会社は落とし込むんですか。
高木:それはもう超シンプルでして、要は格好つけて、綺麗にまとめようとしないってことですね。
高木:というのは、私は経営理念っていう言葉ってあんまりしっくりきてなくて、どっちかというと「経営者の魂の叫び」なんですよ。
田村:詳しく教えてもらって良いですか?
高木:だから、ご自身が経営を通じて何を実現したいのかとか会社をどうしたいのか、従業員さんにどうなってほしいのかみたいなものが絶対経営している以上経営者に思いがあるわけですよ。そんなものを綺麗にまとめるっていうのは抽象的な表現にまとめざるを得ないじゃないですか。
田村:ですね。
高木:お客様の笑顔のためにとか従業員さんの幸せのためにとか、別にそういうのが駄目なんじゃないんですよ。だけどそうやってまとめちゃうと、経営者の本当の魂の叫びが消えるわけじゃないですか。
田村;そうですね。
高木:だからそれだと、田村さんがおっしゃったように、何か感じない。人の心に響かないわけですよ。そこを響かせるためには、ご自身の言葉で、ご自身が思ってることを情熱的に語るしかないんですよ。だから綺麗じゃなくていいんですね。
田村:格言ですね。
高木:なので私がコンサルティングする時っていうのは経営計画に経営理念って絶対入れるんですよね。ですけど、経営理念ってめちゃくちゃ長文だったりするんですよ。
私が代わりに経営理念をまとめるとかってのはやらなくて、私がやるのは、ちょっと「てにをは」を変えたり、それぐらいで基本的には原文そのままにするんですよ。
田村:その経営者から出てきた言葉というか、気持ちをそのまま原文にするんですね。
高木:そう。そこにはやっぱりその人柄とか思いがやっぱり如実に出るんですよね。もうそこはご自分で書かなきゃ駄目ですし、逆にだからそういう文章とか書けないとかってなると、やっぱりまだ掘り下げが足りないですよね。
田村:なるほど。
高木:真剣に何故その事業をやっているのかを紙に書き出して、やっぱりその魂の叫びにしてほしいんです。
田村:魂の叫びっていいですね。経営理念に対する考え方が変わった方もいらっしゃいますね。
高木:そう。だから綺麗にまとめようとしない。経営者の本心をちゃんと出して、文章にするじゃないですか。それを自分の言葉で、従業員さんに伝えるわけですよ。そこも情熱的に語らなきゃいけないですし、綺麗である必要はないんですよね。
田村:なるほど。もう1個質問したいんですけど、結構ホームページとかでも綺麗に収まってるやつもあれば、すごい長文で、もう最初のページからびっしり経営者の思いがページ1枚に載っているホームページもあるんですけど、あれも結構熱苦しいじゃないですか(笑)
結局何が言いたいんだろうみたいな経営理念ってあるじゃないですか。それはそれでいいんですか。
高木:ホームページ見に来る人が、やっぱりいきなり長文だとすると、なかなか読む気にならなかったりするわけじゃないですか。会社の固定的なページには、経営理念を簡潔にまとめたものが載っけられていて、もうそこから入るわけですよ。読み進めていくと経営者のコラムとか出てきて、そこまでのページまで来た人って多少興味を持ってるわけじゃないですか。そこに魂の叫びを入れるんですよ。
田村:なるほど。ちょこちょこ入れていく感じなんですね。
高木:田村さんが「これ本当かよ」って思うのは、ホームページの固定的な部分って明らかに作り込まれてる匂いがするじゃないですか。
田村:そうですね。そういうイメージがあります。
高木:だから、コラムっていうのは不思議なもんで、やっぱり文章を書いた人の人柄も出ますし、定期的に更新されてるものって生きた情報のような感じがするじゃないですか。そこをちゃんとうまく使わなきゃいけないですね。
田村:勉強になるなあ。なるほど。また話戻りますと、多店舗展開していく中で取り組むべき事で、従業員さんに対して自分の会社はこんなふうに考えてるっていうところを伝えていくとお話したと思うんですけど、実務的にはどんな感じでやってくんですか。会社がこういうふうなビジョンがあるんだけど、こういう店舗にしていきたいっていう具体的な実務的な落とし込みはどうするんですか。
高木:会社の方向性をまず示すじゃないですか。それを普段とちょっと違うシチュエーションで言った方がいいと思うんですよ。というのは、例えば普段定期的に行ってる会議の中で、言うとなると、特別感がないじゃないですか。
田村:はい。
高木:経営計画を作って、共有するっていうのは、もうすごく大事な場なんですよね。ただ共有するだけじゃなくて、やっぱり経営者が熱くそれを語れなきゃいけないですし、相手に本気で受け止めてもらわなきゃいけないじゃないですか。だからやっぱり環境も変えた方がいいんですよ。
田村:それは具体的にどういう事でしょうか。
高木:普段例えばお店でミーティングをやってるとかって言ったら、食事ができるようなところを借りて、そこでちゃんとまずモニターに映して情報共有してから食事会をするとか、場所を変えるだけで、もう全然本気度が違いますよね。
田村:それは特別な感じが出てきますね。
高木:そうそう。だからそういったところがテクニックですけど、紙にするっていうのも大事なんですよ。普段そういうのを紙にするとかもなかなかないと思うんですよ。それをちゃんとした資料にして、渡すっていうのも特別感があるじゃないですか。
田村:はい。
高木:そんなところでまずは共有をしていく。
田村:めっちゃいい事聞きました。もう1個質問なんですけども、高木さんがいろんなフランチャイズ本部を見てきた中で、3店舗とか4店舗にしていく段階が一番難しいと言っていたじゃないですか。そんな高木さんだからこそ、自社でできるような、3店舗経営等の店舗展開で重要なことをちょっと教えていただきたいです。
高木:今、会社の方向性としての経営計画の話をしたじゃないですか。店舗ビジネスで、やっぱり大事なのは人のモチベーションを引き出してくる事なんですね。その観点で考えたときにやっぱり会社の道標と同時に、従業員さんがその計画を遂行したときにどうなのかっていう、従業員さんの道標みたいなものも示してあげる必要があるかなと思います。
田村:具体的にそれはどういう事でしょうか。
高木:シンプルに言うと、例えば3年後に5店舗展開するっていう会社の道があるとするじゃないですか。それって従業員さんにとっては他人事ですよ。だから従業員さんは「へえ」とだけ思って、自分事にならないわけですよ。それを自分事に転換しなきゃいけないんですよね。
田村:そうですね。
高木:そうすると、「私はどうなってるんですか」って話ですよ、相手が知りたいのは。
田村:5店舗のうちどこにいるんですかとか。
高木:そうそう。だから5店舗になったときに、例えば新たにこういう仕事が生まれてきますよと。これは当然、今ここで頑張ってくださった方々から、こういった仕事に就いてもらわなきゃいけない。その時には収入というのがどうなるのかとかも大事です。という風に従業員さんもどうなるのかというのを一緒に示すことですよね。
田村:なるほど。この店舗に送るときには、あなたにはこういう仕事を与えてきますよみたいなキャリアマップみたいな事ですね。従業員さんにとっては、自分の覚悟が生まれると思うんですけど、会社にとっては、従業員さんにこの仕事を与えますよってコミットするってことは結構プレッシャーじゃないですか。それって経営者にとって結構不安になったりしないですか。
高木:私がすごく大事にしてることなんですけど、それがいいんですよ。コミットしてやらなきゃいけない状況に自らを追い込むからやるんじゃないですか。できたらいいなみたいな計画はできないわけですよ。じゃなくて「やるんです」。覚悟を決めるためには従業員さんにコミットするんです。やっぱりそこは自分との約束よりも人との約束の方が強いじゃないですか。
田村:そうですね。
高木:なので、これ結構ポイントだと思いますよ。何かやろうと思ったらよく人に言えとかっていうじゃないですか。やらなければいけない状況に自らを追い込む。これはもうおすすめです。
田村:なるほど。この収録以外でも高木さんと僕で打ち合わせしてますけど、何かにコミットしていくっていうのはやっぱり生かされてますね。
高木:そう。コミットして、「やるって言ったらやる」。もうこれがあるだけで良いです。
計画作って形だけのものになってしまったって良くあるじゃないですか。そういう経験がある方はぜひその計画がやらなければいけないものになったかどうかを振り返ってもらいたいんですよね。
田村:なるほど。格言が出ました。高木さんらしくなってましたね(笑)今日はいろいろと多店舗展開すべき際のポイントについて教えていただきました。今日はありがとうございました。
高木:ありがとうございました。
無料メルマガ登録
専門コラムの他、各種ご案内をお届け中です。ぜひ、ご登録ください。

セミナーのご案内
店舗ビジネスの多店舗展開やのれん分け・FCシステム構築を進めていくため、具体的にどう取り組んでいけばいいのか、どのような点に留意すべきか等を分かりやすく解説する実務セミナーを開催しています。
セミナー一覧ぺージへ