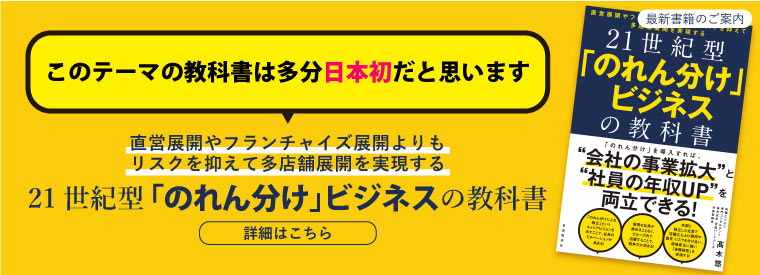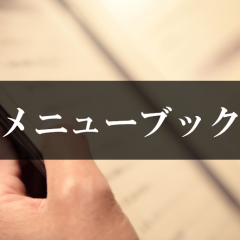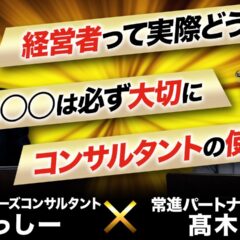コロナウィルスの影響が続いています。
多くのエコノミストが経済の完全回復には、1~2年を要すると予想しているようです。
緊急事態宣言が解除され数か月が経過した今でも、第2波といわれる感染者の推移は、容易に減少する気配を見せません。
このような状況下において、経済活動が再開され、徐々に企業の業績は回復傾向にありますが、一部の業種、とりわけ、旅行や外食、娯楽関連業は非常に大きな影響を受けています。
また、経済が回復したとしても、人々の価値観や生活様式が変わり、元に戻らずに、志向が変わってしまうものもあるはずです。
コロナ前でも顧客ニーズの多様化は進んでいましたが、コロナウィルスの影響により、ますます市場や顧客の動向が読めない状況となってしまいました。
まさに、不確実性の時代です。
今回は、このような不確実性の時代に求められるリーダーの特徴について考察します。
なお、不確実性の高まった時代に求められる「のれん分け制度」構築について詳しく知りたい方はこちらのコラムをご覧ください。
(1)不確実性に高まった時代に必要な経営スタイルとは
このような正解がすぐにわからない時代の企業経営に求められるのは、「多様な意見を受け入れ、試行錯誤し、PDCAサイクルを素早く回すこと」です。
不確実性が高い時代では、すべての取り組みが正解とは限らず、また変化も速いため、対応策の検討に多くの時間を費やすことはできません。
なので、うまくいきそうな取り組みから試し、迅速にレビューして打ち手を変えていく…
この間のスピードが速ければ、たとえ失敗しても、被害を最小限にして、次に活かす経験になります。
そしてこのような経営スタイルには、迅速で活発な情報交換や多様な意見のやりとりが必要になるため、社員を動かすリーダーシップも変えていかなくてはならないでしょう。
従来型のトップダウン形式の支配型ではなく、「社員の自発性を尊重する支援型リーダーシップ」が適していると言えます。
(2)支援型リーダーシップの特徴とは
支援型リーダーシップとは、「社員一人ひとりを支援し、組織目標を達成しようとする」リーダーシップスタイルです。
これは、従来の支配型リーダーシップとは、大きく異なり、以下のような特徴があります。
部下を支援することで組織目標を達成する
支援型リーダーシップは、組織に対する姿勢が支配型リーダーシップと異なります。
支配型では、上司自らリーダーとして組織を引っ張り、成果を出そうとしますが、支援型では、部下を支援することで、組織の目標を達成します。
上司が組織の上に立つのではなく、組織の下から社員をバックアップするイメージです。
目標達成後の満足感が高まる
どちらのスタイルもリーダーシップの目的である組織目標を達成することは同じですが、そのプロセスが異なるため、達成後の社員の満足度が異なります。
支配型では、上司と一部の頑張った社員の達成感が高くなるようです。
一方、支援型では、社員それぞれが自分の持てるスキルや考えを発揮することにより、組織全体での満足感が高くなります。
部下を信頼感で動かす
支配型リーダーシップは、部下を命令や指示で動かしますが、支援型リーダーシップは信頼感で動かします。
具体的には、支配型リーダーは、自ら経営方針を示し、部下をその方向に向かわせることで仕事を前に進めますが、支援型リーダーは、部下の考えや行動を尊重し、仕事を任せることで進めます。
これには、上司と部下との間で強い信頼感が必要です。
正解か何かわからない課題に取り組むためには、信頼感が醸成されていないと、部下は思い切ってチャレンジすることができません。
双方向のコミュニケーションを増やす
支援型リーダーシップは、組織のなかで多様な意見を受け入れ、対応策を実行していきます。
そのためコミュニケーションは、上司と部下において、双方向で行われます。
上司からの一方的な指示や命令ではなく、傾聴により部下の考えを引き出すようになるからです。
またコミュニケーションの頻度は、こまめに回数を増やすことを意識します。
リーダーは部下の影響で成長する
支援型リーダーの成長は、部下からの影響によってもたらされます。
支配型リーダーのように、自己を磨くことも大切ですが、これだけでは、多様な考え方の吸収やスキルの習得は十分とは言えません。
部下との対話や行動などの関りを通じて、部下を成長させるとともに、上司も成長します。
上司と部下の成長のポジティブサイクルです。
成果は部下の結果と評価する
成果の評価については、人間誰でも自分の成果を強調したくなるものです。
人は評価されることを1つのモチベーションとして行動しますので、やみくもに否定できるものでもありません。
しかし、支援型リーダーは、まず部下の評価を重視します。
組織目標が達成できたことは、部下の取り組みの結果であり、部下の成果だと考えます。
そして、部下が成果を出せるように支援したことや成長させたことが、上司の評価となるのです。
自らの結果と考えるか、部下の成果の結果と考えるかの違いです。
PDCA管理を重視する
支援型リーダーはPDCA管理を重視します。
PDCA管理とは、Plan=計画、Do=実行、Check=評価、Action=改善の一連の取り組みのことです。
常に自社の取り組みと結果をレビューし、取り組みを改善させるこの管理サイクルを高速で回すことが必要です。
なぜなら、不確実性が高い時代において、すべての取り組みが正解とは限らないからです。
失敗を受け入れる
支援型リーダーは、失敗を受け入れる用意があります。
すべての取り組みが成功するとは限らないことを知っているからです。
そのため、自らの考え方や取り組みに固執することなく、失敗から学ぶ姿勢を持っています。
同時に、多様な意見を尊重する、試してみる、失敗を受け入れる、レビューするといったことに寛容な組織風土を醸成することに努めます。
(3)自発的な人材を育成し社員が活躍できる組織風土を醸成する支援型リーダーシップ
このように支援型リーダーシップは、経済が右肩上がりで成長していた時代に適していた従来の支配型リーダーシップとは多くの点が異なります。
経済成長していた時代には、もしかしたら間違っていたかもしれない取り組みが、市場の成長によりカバーされてしまっていたかもしれません。
しかし、今は不確実性の時代です。
1つの考え方に固執した一か八かの取り組みではなく、ポテンヒットでも小さな成功を積み重ねていくことが必要です。
これには、部下が自発的に考え、行動できるような人材育成を行うとともに、社員一人ひとりが活躍できる組織風土を醸成することが求められるのです。
(コンサルタント・中小企業診断士 木下岳之)
無料メルマガ登録
専門コラムの他、各種ご案内をお届け中です。ぜひ、ご登録ください。

セミナーのご案内
店舗ビジネスの多店舗展開やのれん分け・FCシステム構築を進めていくため、具体的にどう取り組んでいけばいいのか、どのような点に留意すべきか等を分かりやすく解説する実務セミナーを開催しています。
セミナー一覧ぺージへ