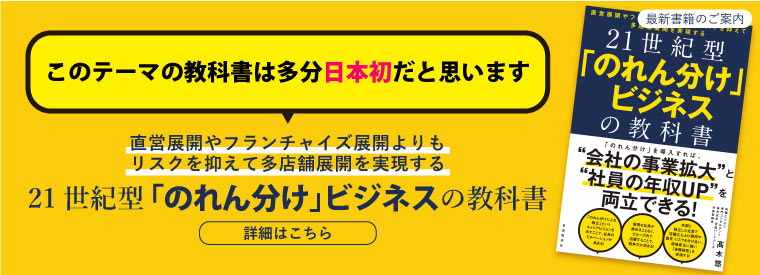最近の若者の多くは、内向的でおとなしく対面で自己主張をしないと言われます。
また、何をしたらよいのか迷っていたり、自分の将来の仕事について不安を抱いている人が少なくなく、
会社などの社会性のある組織の中では受け身的な姿勢になりがちです。
しかし、現在の業務が自分の成長につながることがわかれば、とても前向きに行動するようになります。
そこで、その気づきと機会を与えるために、短期と長期の2つの視点を活用して若い社員の自発性を引き出す取り組み方についてご紹介します。
なお、店舗ビジネスのキャリアの限界を突破する「のれん分け制度」づくりや成功のポイントを知りたい方はこちらのコラムをご覧ください。
(1)入社から2~3カ月してもおとなしい新入社員
「仕事はしっかりやってくれるのですが、あまり自分から動くタイプではないようです」
これは先日サービス業の経営者から伺った言葉です。
この会社では、会社の成長にともない社員が不足している状況が続いていました。
しかし、コロナ禍により以前より優秀な人材を採用しやすくなっているため、少数精鋭でぜひ採りたいという人材がいれば採用してきました。
そして、しっかり会社に貢献してもらうために人材育成にも力を入れました。
事業や業務について理解を深める研修を準備したり、実際の業務では先輩社員を補佐役としてつけたり、業務を習得しやすくするように配慮しました。
ところが、ある新入社員が先輩社員から作業指導を受け始めて2~3カ月経過したころ、経営者はその社員の消極的な行動が気になるようになりました。
はじめのうちは新しい職場や慣れない環境で誰もがおとなしくなりがちですが、2~3カ月もすれば次第に慣れてきて元気に働いてくれるだろうと、この経営者の方は想像していました。
しかしどうやら慣れていないからではない、ということがわかってきたのです。
(2)若い社員には業務の意味と将来のキャリア形成に役立つことを伝える
最近の若者の多くは、内向的でおとなしく対面で自己主張をしないと言われます。
少子化やスマホなどの影響により、自分と異なる環境や意見に接することを得意としていません。
そのため、どのように動いたらよいかわからない場合では、自分から積極的に質問したりせず、教えてもらうことを待っていたりします。
また、コロナウィルスなど明るいニュースが少ないなか、将来になかなか希望を見い出せず、何をしたらよいのか迷っていたり、自分の将来の仕事について不安を抱いている人が少なくないようです。
そのために、会社などの社会性のある組織の中では受け身的な姿勢になりがちです。
このような若い人に対しては、業務習得のサポートをしっかりしながら、その業務の意味を教え、さらに、その取り組みが将来のためのキャリア形成に役立つことを伝えることです。
現在の業務が自分の成長につながることがわかれば、とても前向きに行動するようになります。
その気づきと機会を与えることがこのような若い社員を自発的人材に育成するためのポイントです。
(3)2つの視点を活用して若い社員の自発性を引き出す
その気づきと機会を与えるためには、短期的な視点と長期的な視点の2つがあります。
短期的な視点
成功体験を積ませる
社員が担当する業務をしっかり遂行できるようになることは会社と社員どちらにとっても大切なことです。
会社にとっては社員に仕事を任せることをでき、社員にとっては成功体験を積み自信がつくからです。
業務指導を受ける社員は誰でも不安な気持ちを持っています。
その不安な気持ちを取り除くには、その作業ができることになる以外に方法はありません。
そこで、簡単な業務から始め、少しずつ作業内容を難しくしていきます。
たとえ小さな作業でもその作業ができるようになることはうれしいことです。
作業を通じて達成感を味わい自信を深めることで、安心して業務に向かえるようになります。
難しい作業は必ず細分化します。
作業の意味や目的を説明する
作業の意味や目的を説明するように心がけます。
どのような作業でも1つで完結する業務はありません。
必ず次の作業工程が社内にあったり、その製品やサービスが他社に供給されたり、お客様に提供されたりします。
アウトプットを受け取る人が望んでいることを説明します。
また、そのような作業を続けることで、社員にどのようなスキルが身につき、次に期待されている作業や能力が何であるかを伝えます。
このように作業が次にどのようにかかわっているかがわかれば、どうすればさらに速く効率的に作業ができるかや、アウトプットの品質や出来栄えなどについて、いっそう興味が持てるようになります。
長期的な視点
キャリア形成支援
社員が将来なりたい姿を共有し、そのためのロードマップを描いたり、計画したりすることを支援します。
具体的には、この会社にはどのような職種があり、この会社で働くことでどのようなスキルが身につき、いつどのような役職につくことができるのか、またそのときの収入はいくらかなどをアドバイスします。
将来に不安があるということは、将来の自分が働いて生活している姿をイメージできないからです。
そこで、将来の可能性のある姿を示すことで、持続的なモチベーションの形成に役立ちます。
最近ではこれらの情報を積極的に開示する会社が増えています。
スキルアップ支援
キャリア形成支援で具体的な将来の姿をイメージさせたら、その姿になれるようにスキルアップを支援します。
キャリアは会社で働いた時間が経過すれば自動的に形成されるわけではありません。
求められるスキルを計画的に身につけていく必要があります。
例えば、飲食店のホールでは、一般社員の業務は開店前の準備から接客、または売上促進まで多岐にわたります。
そして、実務経験のある社員に対しては、業務の効率化や顧客フィードバックの活用などステップアップした業務や、さらに経験に応じて担当するグループのマネジメントなどが求められるかもしれません。その実現のためにスキル開発の計画を社員と一緒になって立案し、会社が研修や人材配置などの機会を積極的に提供します。
このように、若い社員の状況を察し適切なサポートをすることで、若い社員が前向きに行動できるようになります。
ジェネレーションZと呼ばれるような20代前後の社員は、より仕事と生活のバランスを重視したり、自分に向いている仕事や合っている環境を優先してすぐに仕事をやめたり、転職を繰り返す傾向があると言われています。
しかし、心のなかにある前向きな気持ちを丁寧に引き出すことで、自発的な人材に育成できるでしょう。
(コンサルタント・中小企業診断士 木下岳之)
無料メルマガ登録
専門コラムの他、各種ご案内をお届け中です。ぜひ、ご登録ください。

セミナーのご案内
店舗ビジネスの多店舗展開やのれん分け・FCシステム構築を進めていくため、具体的にどう取り組んでいけばいいのか、どのような点に留意すべきか等を分かりやすく解説する実務セミナーを開催しています。
セミナー一覧ぺージへ