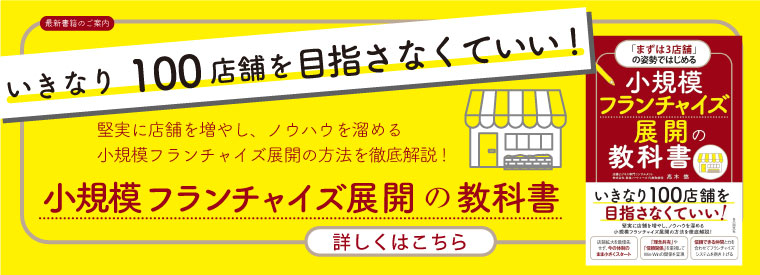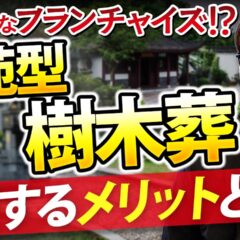コロナウィルスが社会問題化して人と人の接触が制限され、IT化が一層進展しました。
これを機会に、業務の効率化や改善を図るためにIT化を進めなくてはならないと考えている経営者も多いでしょう。
IT化は、デジタル機器や情報と親和性の高い若い世代を活用し、会社の成長につなげる機会ともいえ、「若い世代を自発的人材に育成するための業務改善のチェックポイント」についてご説明します。
なお、店舗ビジネスのキャリアの限界を突破する「のれん分け制度」づくりや成功のポイントを知りたい方はこちらのコラムをご覧ください。
コロナ禍でIT化がいっそう深化
コロナウィルスが社会問題化し人々の生活や働き方を変えてから2年以上が経ちました。
今回のコロナウィルスの影響は計り知れませんでした。
人々の考え方自体を変えたのはもちろんですが、より大きな変化であると筆者が考えることは、IT化の進展です。
ご存じの通り、IT化は以前も着実に進んでいました。
身近なところでは、スマホ決済やe-commerce、事業運営では、仕入れから売上げまでの情報の一元管理や在庫の補充、SNSを活用した販売促進などです。
しかし、このコロナ禍でそれがさらに深化したようです。
コロナ以前では、国や自治体などが2020年の東京オリンピックに向けて、大会開催中の公共交通機関の混雑緩和のため、リモートワークを推進していましたが、正式に導入している企業は一部の企業のみでした。
それが今やリモートワークは当たり前になりました。
そのためのツールや施設なども一般的になりました。
携帯の料金も値下がりし、Wi-Fiはどこでもつながりやすくなりました。
よりIT化が身近になり、パーソナルな領域に浸透してきたと感じます。
IT化により業務改善を実施する
ITがそれほど進展していない時代を知っている世代は、現在の急速な変化を感じやすいですが、IT機器やデジタル情報を子供のころから使いこなしている現代の若い世代は、これが当たり前の世の中だと思っています。
受験勉強にしても、以前であれば、例えば、英語の単語を調べるためには辞書を引いていました。
勉強するためには、重い辞書を持ち歩く必要がありました。
ところが、現代の若者は、辞書をほとんど使ったことがなく、スマホなどで検索することで解決します。紙やペンを使う機会がめっきり減り、スマホやPCでほとんどの用を足すようになっています。
このような若い世代が入社してくる時代ですが、受け入れる準備ができているでしょうか?
もちろん、若い世代に迎合するために、IT化を推進するのではありません。
業務の効率化や改善を図るためにIT化を図るのです。
例えば、紙には一覧性などの良さがありますが、IT化には個人に合わせた情報が得られるといったパーソナル化などのメリットがあります。
業務内容を見極め効率的な業務改善を実施することにより、若い世代にも業務がより馴染みやすいものになります。
現代の若者はデジタル機器や情報を扱うことにとても慣れているため、非効率な業務を敬遠する傾向があると言われています。
若い世代を自発的人材に育成する業務改善のチェックポイントとは
そこで、IT化推進による業務改善を図るため、デジタル機器や情報と親和性の高い若い世代を活用します。
若い世代がITを利用し自発的に行動できるようになることで、会社を活性化します。
若い世代が年上の世代と異なり扱いづらいと消極的になるのではなく、逆に若い世代を強みして機会であるIT化を推進し、会社を成長させる作戦です。
このような世代を自ら行動できる自発的人材に育成することがこれからの重要な経営課題の1つです。そこで、以下のようなチェックポイントを意識して、若い世代を動機づける取り組みを行いましょう。
経営方針として業務改善を社内に浸透させる
業務改善の目的を社内に伝えます。
業務を効率化することが目的であり、IT化が目的ではありません。
IT化は手段です。
IT化により従来よりも業務が迅速になったり、情報の検索が容易になったりすることで、結果として社員や顧客の満足度が高まります。
IT化が目的になってしまうと、システムを導入しても期待していた成果がでなかったり、不慣れな社員から反発を受けたりすることがあります。
このような事態を避けるために、事前に業務改善を経営方針の1つとして、社内に浸透させます。
合理的な業務プロセスと適切な判断になっているか確認する
現在の業務プロセスは定量的もしくは確実性の高い情報をもとに構築されているでしょうか。
また、経営判断は論理的に行われているでしょうか。
ヒト、モノ、カネ、情報の経営資源が大きくない中小企業では、すべてのプロセスが理論的に構築され、すべての判断が客観的にされているとは限りませんが、しっかり事業をプランに沿って進める必要があります。
なぜそのやり方をするのか?
なぜその判断をしたのか?
確実に説明でき納得性が高いものでなければいけません。
施策が成功するかしないかは外的要因の影響も受けますが、自社の対応策が合理的であることを事前に確認しておく必要があります。
合理的な仕組みがあれば、若い世代の能力も活かしやすくなります。
例えば、広告などの販売促進策は費用対効果を検証します。
以前から新聞や雑誌にチラシを入れているからといって惰性でやってはいけません。
また、他社がやっているからといってただ自社のWEBやSNSのアカウントを立ち上げ、情報をアップしても仕方ありません。
顧客が知りたい情報をつかんで情報を適時アップデートする必要があります。
また、アクセスや検索のしやすさも考慮する必要があります。
従来からやっているからとか、過去にうまくいったからといった成功体験だけに頼って、事業を展開すべきではありません。
過去の成功体験でモノを語ることは若い世代からは忌避されます。
顧客の志向やIT環境などの社会環境は刻々と変わっていますので、現在の状況に鑑み、業務プロセス構築と判断を行います。
業務改善に加えて留意したいこと
IT化による業務改善と同時に社員のキャリアマップを作成し見える化することはとても大切です。
業務の専門性や習熟度、勤務年数などに応じて、この先3年、5年、10年程度までを見通した個人の計画を立案します。
若い世代は合理的で短期的視点である一方、将来に対して大きな期待もできず不安を持ち合わせています。
そのため、会社の業務を達成することで、自分にどのようなスキルが身につき、どのように成長できるのか、計画的に知りたがっています。
年上の世代のように、上司や先輩の背中を見て仕事を覚えろといってもついてきません。
さらに、多くの残業や職場環境の暑い寒いがあったり、身体的につらい業務が長いなど労働環境が厳しい仕事ではすぐにやめてしまうかもしれません。
そこで、目的を達成することで何を得ることができるのか明確にしておきます。
職場での知識と経験に頼った能力の習得だけにならないようにします。
特に年配の世代では、OJT(オン・ザ・ジョブトレーニング=職場での実務を通じた職業訓練)が教育の中心であり、研修や講習などの体系的な教育手段が乏しかったケースがあります。
このような経験をもとに、若い世代に対して、「オレの作業を見て真似しろ」や「お前ならできるはずだ」などの気合を前面に出した声掛けは逆効果になりかねません。
これらのチェックポイントと留意点を意識し、若い世代を自発的人材に育成するための業務改善を実施します。
(コンサルタント・中小企業診断士 木下岳之)
無料メルマガ登録
専門コラムの他、各種ご案内をお届け中です。ぜひ、ご登録ください。

セミナーのご案内
店舗ビジネスの多店舗展開やのれん分け・FCシステム構築を進めていくため、具体的にどう取り組んでいけばいいのか、どのような点に留意すべきか等を分かりやすく解説する実務セミナーを開催しています。
セミナー一覧ぺージへ