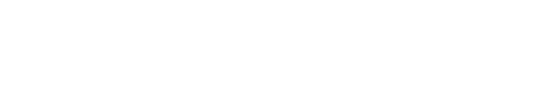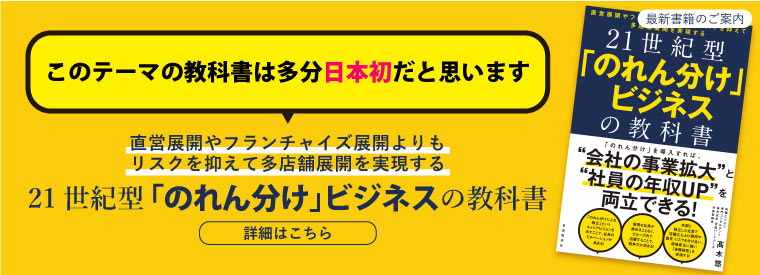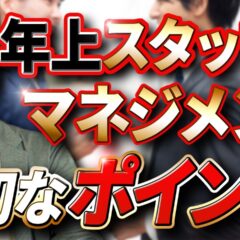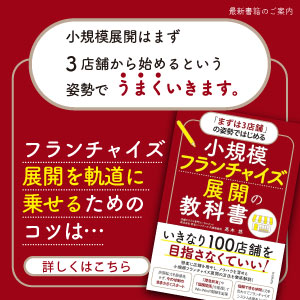ネットラジオ『多店舗化・フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所』は、弊社代表の高木と社労士の田村陽太が、飲食店、整体院、美容院等の様々な店舗ビジネスの「多店舗展開」を加速させるために重要な事を対談形式でお話しするラジオ番組です。
【ハイライト】
・本部と加盟者間の信頼作りについて
・SVが管理すべき適正な加盟店数とは?
・レベルが高いSVとは?
・SVが身につけるべきコミュニケーション術
・本部がSVを教育する上でのポイント
多店舗化・フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所。この番組は株式会社常進パートナーズの提供でお送りいたします。
店舗ビジネス専門コンサルタントの高木悠が最速・最短で年商30億、店舗数30超を実現する実証されたノウハウをコンセプトにのれん分け制度構築、FC本部立ち上げ、立て直し、人事評価制度の整備など飲食店、整体院、美容院などの様々なビジネスの多店舗展開を加速させるために重要なことを対談形式で分かりやすくお話しする番組です。
田村:こんにちは。パーソナリティーの田村陽太です。配信第15回目となりました。本番組のメインパーソナリティーをご紹介します。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木悠さんです。よろしくお願いします。
高木:よろしくお願いします。
田村:今日は、前回「スーパーバイザーってどんな役割を果たすんでしょうか?」っていう質問のお話を聞かせていただきまして、スーパーバイザーっていうのはやっぱり加盟者の利益を出していかなきゃいけないとか、あとは本部のルールを守らせなきゃいけない等、いろいろ役割を担っているとお聞きしました。
最後の方に三つ目の役割があるっていうお話をしていて、そこら辺の話をもっと聞きたいのと、あとこれからスーパーバイザーをうまく活用して、フランチャイズをうまくやっていきたいっていう会社さんが多いと思うんですけど、そういう制度運用についてのポイント、あとは、高木さんは結構スーパーバイザーとして長い経験をされてると思うので、経営者に好かれるコツなどのコミュニケーション術みたいなものがおありだと思うので、高木さんなりの「スーパーバイザーはこうあれ!!」みたいなことをお聞きしたいなと思います。
高木:なるほど。まずそのスーパーバイザーの役割の3つ目、本部と加盟者の信頼関係作りの事についてです。本部と加盟者が結局は人と人の関係になるわけじゃないですか。加盟する前っていうのは、例えばその本部の経営者と加盟店の経営者が会ったりするわけですよ。
田村:はい。
高木:営業の方とかと会ったりするわけじゃないですか。だけど実際開業したら、本部と加盟店の接点ってどうなるのって言ったら、これSV以外なくなるんですね。
田村:そうなんですか。
高木:そう。他に会う人って普通の場合ないんですよ。年に1回とか年に2回とかオーナー会議とかがあったりして、本部の経営者同士が会ったりするってことは当然あるんですけど、日々コミュニケーションを取るっていうのはもう基本スーパーバイザーしかない。
田村:なるほど、本部とのやりとりは、スーパーバイザーを介してやっていくみたいな。
高木:そうですね。加盟店は普通本部に対してロイヤリティを払ってるわけじゃないですか。
お金だけ払ってて、お金払ってる人と合わないとかってなったら、それはもう信頼関係もないですよね。
田村:そうですね。
高木:だから必ずスーパーバイザーっていうのを配置して、本部と加盟店の信頼関係を維持していくためにやっぱり定期的に接触して、本部の方針をちゃんと伝えて理解してもらう必要があります。当然加盟店にもいろいろ事情があるわけじゃないですか。本部が言うことを聞きたくないときもあるわけですよ。そういうのもちゃんとSVは聞いて本部にフィードバックをして、そこの関係を円滑にするというか、信頼関係を作っていくっていうのがもうスーパーバイザーの役割になるんですね。
田村:なるほど。ちょっと一つ質問したいんですけど、フランチャイズの本部っていろんな形があると思うんですけど、スーパーバイザーが見るべき加盟者の数はどれぐらいが平均なんですか。どれぐらい見られてるんですか?
高木:これは本部によってまちまちだと思うんですよ。
例えば、その週に1回店舗を臨店する、例えばコンビニとかそうだと思うんですけど、週に1回臨店するって言ったらどう考えたって一日に2店舗回ったって1週間で10店舗ぐらいじゃないですか、。
田村:はい。
高木:月に1回とかってなってくると、20営業日ありますからね。週に1回ぐらいは社内で何かやる日ってとらえても、自分の持てる加盟者は15、16店舗ぐらいですかね。結構多いのは10店舗から15店舗ぐらいが多いんじゃないですかね。
田村:結構大変ですね。高木さんが思うに、そのスーパーバイザーが見れるべき数、どれぐらいが適正なんですか。どれぐらいにすれば、加盟者の満足度を高められるとか本部の利益に繋がるような、スーパーバイザーの仕事ができる数なんですかね。
高木:ロイヤリティをどれぐらい加盟者からもらってるかによって、そこに費やせるかの人件費で変わってきますね。当然加盟者の数が少なければ少ないほど、スーパーバイザーとしてはやりやすいんですよね。だけどそこにそんなに費やせない事情もあると。感覚で言ったら10店舗から15店舗ぐらいだったら、レベルが高いSVだったら問題なく回せるかと。
田村:なるほど。SVが見る店舗数が少ないと、フランチャイズからロイヤリティを高めてるってことですね。本部のロイヤリティの料金というか。
高木:そうですね。結局加盟店から払ってもらうロイヤリティで本部のスーパーバイザーの人件費が出てるわけですから。よくロイヤリティが高いか低いかどうかっていう質問されるんですけど、それだけ見てもあまり意味がなくて、そこにどんなサービスがついてるかが大事です。だからコンビニってよくロイヤリティが高いと言って文句言う方もいるんですけど、だって週に1回スーパーバイザーが来るって言ったら、もうそれだけで大変な人件費ですよ。
田村:そうですよね。密に来てくれるっていうのはその分、本部に対するロイヤリティも高くなるってことですよね。もう1個質問なんですけど、高木さんが先ほどスーパーバイザーにもレベルが高い低いがあるって言ってたじゃないですか。SVの高い低いを決める項目って何かあるんですか、この人はレベル高い、低いってどこを見てそれを決めるのですか。
高木:まず先ほどお話した本部と加盟店の信頼関係作りができてるかどうかっていうところが一つポイントだと思っていて、例えばスーパーバイザーをやっていて一番簡単なのって加盟店が言うことに迎合することなわけですよ。
田村:なるほど。
高木:だから加盟店が、「本部がこんなことやってるんだけど、これもうどうしようもないよね。」と言ったら、スーパーバイザーも「いや~そうですよね。僕もそう思うんですよ。」みたいなことを言ってれば、スーパーバイザー個人と加盟店の信頼関係って作れるわけですよ。
田村:できましたね、そこは。
高木:人間関係ができていくわけですよ。でもそれってもう本部と加盟店の信頼関係は最悪じゃないですか。だからそこですよね。加盟店の言ってることはわかるよと。でもその本部が言ってることもわかってよと。そこでうまい事やっぱ着地させなきゃいけないわけです。
田村:そうですね。
高木:それができるかどうかなんですよ。
田村:なるほど。それについて高木さんの次の質問に絡めてお聞きしたいんですけど、高木さんなりのスーパーバイザーとしての加盟者へのコミュニケーション術、どんな風に接していけばいいのかってところのキモをちょっと教えていただきたいんですけど。
高木:でもこれは個人としてやることと、組織としてやる仕組みとして運用していくっていうところで考えられると思うんですけど。まず個人としてやるっていうことを考えたらもうとにかくその加盟店の経営とか店舗の運営とかについてSVが一生懸命やるってことですよ。
田村:一生懸命やるとはどういう事でしょうか。
高木:スーパーバイザーってフランチャイズ本部の社員じゃないですか。だから、どうしてもそのフランチャイズ本部のため、フランチャイズ本部の利益の方に走りやすいわけですよ。でもその姿勢がある限り、その加盟店オーナーとか加盟店の店長との間の人間関係っていうのは作れないんですよね。だから、やっぱフランチャイズ本部の人間なんだけど、だけど一旦それを置いといて、加盟店に行ったら、加盟店の利益とか店舗運営をいかに良くするかっていうのを、それこそ相手の会社の社員になったつもりで、一生懸命な姿勢を見せる事が、個人としてはもうそれが全てだと思いますね。
田村:なるほど。具体的にどんなことをするんですか?店舗のどんなところをたくさんやったんですか?
高木:例えば、店舗にいたときに、基本的にスーパーバイザーって何か加盟店の代わりに何かしてあげるような必要はないわけですよ。だからオペレーションに入ってあげたりとかそういう必要はないんですよね。
田村:はい。
高木:だけど、例えばその店舗に行って面談とかが終わって、一通りチェックとかし終わった後に、ちょっとお客さんが入ってないから、僕チラシ配ってきますよみたいな姿勢があるだけで、もう社長から見たらこいつはいいやつだなと思うわけじゃないですか。
田村:頑張ってるな、こいつみたいな。
高木:そういう姿勢をどれだけ見せられるかってことだと思います。
田村:なるほど。時間を見つけて加盟者のためにやろうかなっていうのを見つけていく感じですね、時間をね。
高木:ちょっとでもいいから、やっぱりその相手に寄り添って、相手に貢献しようとする姿勢を見せることですよね。
田村:なるほど。都度発言していくんですね、経営者に対して。俺も参画しますよ、みたいな。
高木:そう。もう何でもいいですよね。例えばちょっと忙しそうだったら皿洗いやりますよとか。もうスーツで皿洗いやるとか変なんですけど(笑)だけど、やっぱそういう姿勢を見たら、それを見て嫌がる人なんていないわけですよ。
田村:いないでしょうね。必死だなこいつと思いますもんね。
高木:そう。まずそういったところですよね。
田村:なるほど。高木さんもスーツを着られてて、泥んこといったらあれですけど、常に経営者に対して、頑張っているという感じの姿勢を見せていたのが大事だなと思いましたね。
高木:やっぱりいきなりすぐできるわけじゃないので、僕も失敗を繰り返して、SVとはどうあるべきかを考えて、やっぱり行き着いたところっていうのが、言葉で何か言うとかも大事なんですけど、まずその姿勢を見せるのが一番早いよねっていう事です。
田村:なるほど。すごい良い事聞きました。スーパーバイザーの方もこの番組聞かれてると思いますので、SVとしてあるべき姿勢について勉強できたのかなと思います。高木さん、いろいろとスーパーバイザーの役割のお話を聞かせてもらったんですけども、スーパーバイザー制度を運用する際の本部のキモとなるポイント、整理というかおさらいというか、お話していってほしいなと思います。
高木:これは、今個人のお話をしましたけど、本部として仕組みとして回していくんであれば、やっぱりそれは個人に依存しては駄目という事ですよね。
田村:それはどういう事でしょうか。
高木:個人が頑張る姿勢を見せたらいいよって話をしたんですけど、本部はそこに頼ってちゃ駄目なわけですよ。やっぱり本部は、スーパーバイザーがきっちりとした対応をして加盟店を満足させられるような仕組みを作んなきゃいけないけわけですよ、当然教育も必要なんですけど。
田村:はい。
高木:やんなきゃいけないポイントっていろいろあると思うんですけど。ポイントを絞るんであれば、店舗にスーパーバイザーが行くときに、好き勝手にさせないというか、準備しないで行くようなことだけは避けた方がいいよってことですね。
田村:なるほど、それは具体的にどういうことでしょうか?
高木:例えば、その店舗に行くからには、何か目的があって行くわけじゃないですか。当然行かなきゃいけないっていう契約上のルールもあるんでしょうけど、その構図的なところに立ち返ると、まずそこに行って、何か目的を果たしてくるのがスーパーバイザーの役割なわけですよ。
田村:そうですね。
高木:だけど月に一回行くみたいなルーティンになってると、そこに行って、なんとなく会話してチェックして帰ってくるスーパーバイザーみたいなのが出てくるわけですよね。そうなってしまうとスーパーバイザー個人の資質に委ねられるわけじゃないですか。
田村:そうですね。
高木:だからそうじゃなくて、例えばスーパーバイザーが店舗に行く際に、臨店する際のまず目的は何ですか?と聞く事が大事です。目的を実現するためには、例えば面談はどういう話の構成で進めていくのかとか、目的を実現するためには解決しなきゃいけない問題もあったりするわけですよ。
田村:そうですよね。
高木:この加盟店はこういうことに対してネガティブな反応をしてくる可能性があるとか、分かるわけですよ。それに対して、そういうネガティブな反応されたときに加盟店を説得して言うことを聞いてもらなきゃいけないんですから、どうするかみたいなところを準備しとかなきゃいけないですね。
田村:そうですね。
高木:そういうのをちゃんと作るような仕組みにして、そういうのを作るスーパーバイザーの訓練を本部がして、加盟者の所に行かせるようにするとか大事ですね。
田村:教育ってすごい大事なんですね。
高木:とにかくその目的意識がないところに行っちゃったらそれこそ何も生まれないですよね。
田村:そうですよね。一つ質問したいんですけども、本部がスーパーバイザーを教育するっていうのはどんな風にしていくのですか。面談の機会を設けるんですか。誰が担当するかとかもあるんですか。
高木:いろんな方法があるんですけど。私がおすすめしたいのは、特定のシチュエーションを設定して、私はよく「面談の設計」って呼んでるんですけど、その面談で実現するゴールは何かとか、どういう筋書きで話を進めていくかとか、そういったものをちゃんと作ったら、先輩のスーパーバイザーとかに経営者役をやってもらって、ロールプレイングとかするわけですよ。
田村:そんなんやってるんですか。
高木:そういうのをやって、先輩スーパーバイザーはちょっと意地悪な投げかけとかするわけですよ。「いや、でもそれはなあ。」とか、「うち赤字になっちゃうよ!」とか言ってもらうんですよ。
田村:はい。
高木:それに対して、どういう返しができるかみたいな、やっぱり加盟店で練習するわけにいかないですから、最初はそういった先輩とかの練習をしてから現場デビューした方がいいですね。
田村:ロープレしてくんですね、そこはね。なるほど、そこで慣らしていって、加盟者の社長さんにもしっかりとそういうところが説明できるように訓練していくっていうのが大事ですね。
高木:そうですね。
田村:なるほど、いいこと聞きました。今回と前回で、フランチャイズのスーパーバイザー、どういうふうにして教育していくかとか制度作りをどうやってくいくかっていうお話を聞かせてもらったんですけど、非常にいいお話が聞けたと思います。
高木:はい、よかったです。
田村:高木さん、今回もありがとうございました。
高木:はい、ありがとうございました。
無料資料ダウンロード
FC本部立ち上げを進めていく際の手順やポイントをまとめた資料を無料進呈しています。宜しければ、下記よりダウンロードください。

セミナーのご案内
店舗ビジネスの多店舗展開やのれん分け・FCシステム構築を進めていくため、具体的にどう取り組んでいけばいいのか、どのような点に留意すべきか等を分かりやすく解説する実務セミナーを開催しています。
セミナー一覧ぺージへ