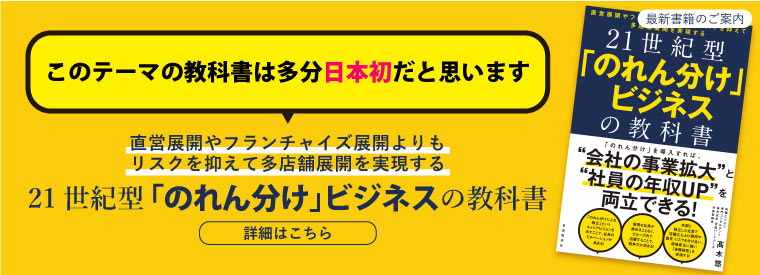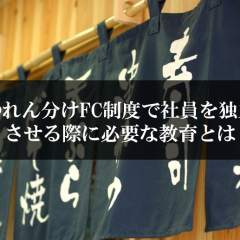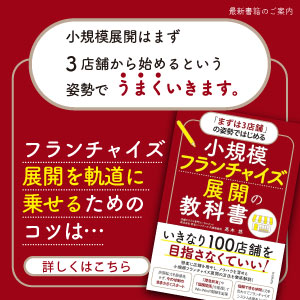数年前の内閣府による日本を含めた7カ国の若者を対象とした意識調査によると、日本の若者の自己肯定感が他国に比べて、著しく低い結果でした。
日本の社会には、社会規範やチームワークを重視する考え方が尊重されますが、現代は不確実性の時代です。
高度成長時代とは異なり、この不透明な時代に会社を成長に導くには、組織として力を結集するとともに、一人一人の個の力を高めることが必要です。
個の力とは、社員それぞれが自発的に考え、行動する姿勢のことです。
今回は、個の力を発揮させるために必要な「自己肯定感を高める対話方法」について考察します。
自己肯定感が低いとされる日本の若者
先日ある興味深い調査結果を目にしました。
数年前の内閣府による日本を含めた7カ国の満13~29歳の若者を対象とした意識調査でした。
これによると日本の若者の自己肯定感が他国に比べて、著しく低い結果でした。
例えば、「自分自身に満足している」という質問に対して、自分自身があてはまると回答した割合は、 日本45.8%、韓国71.5%、アメリカ86.0%でした(他の西欧諸国はアメリカと同様の傾向なので省略します)。
また、「うまくいくかわからないことに対し意欲的に取り組む」に対しては、日本52.2%、韓国71.2%、アメリカ79.3%でした。
一方、別の質問もありました。
「自国のために役立つことをしたいと思っている」に対しては、 日本54.5%、韓国43.2%、アメリカ42.4%となっており、日本は他国に比べて、高い数値になっています。
これらの調査結果がまず示していることは、日本の若者は他国に比べて、自分の価値や存在を肯定する自己肯定感が低く、積極性に欠けるということです。
一方、自国に対する帰属、貢献意識が高いと言えます。
これはどういうことを意味しているのでしょうか?
しばしば新聞や雑誌の記事などで、日本人は自己肯定感が低いといった論調の記事を見かけます。
そのため、もっと人を評価して、ほめるようにしよう、と結論づけるものもあるようです。
筆者はその方向性は間違っていないと考えますが、そのような指摘を聞いて久しく、日本の学校や職場がそのようにシフトしてきたかみてみると、従来よりはよくなったかもしれないが、大きくは変わってないのではないのか、というのが現在の社会から受ける率直な印象です。
不確実性の時代には社員の自己肯定感の向上が欠かせない
一方、自国に対する帰属、貢献意識が高い点については、日本の社会では、社会規範やチームワークを重視し、組織の中で適切に行動し、組織としての目的達成が尊重されることが影響していると思われます。
個人で達成できないことを組織で達成しようとするのです。
この結果として、会社が組織的に、消費者や顧客に対して、満足のいくサービスや商品を提供できています。
例えば、購入した商品に関する問い合わせの際、担当者によって対応がまったく異なったり、店舗などで店員によって著しく提供するサービスが異なったりということはほとんどないでしょう。
日本では当たり前ですが、グローバルにみると日本企業の特徴ともいえ、その根底にあるのが上記の考え方、意識といえるでしょう。
しかし、現代は不確実性の時代です。
高度成長時代とは異なり、日本の社会は少子高齢化に直面しています。
この不透明な時代に会社を成長に導くには、組織として力を結集することとともに、その個の力を高めることが必要です。
個の力とは、「社員一人ひとりが自発的に考え、行動する姿勢を持つこと」です。
そして個の力を発揮させるためには、調査結果で低かった「自己肯定感を高めること」が重要です。
積極的に仕事に取り組んだり、新しいことにチャレンジしたりするために、自己肯定感は欠かせないからです。
先日ある経営者の方が発した言葉がずっと耳に残っています。
その経営者は、社員からの確認や提案などに対する返事をする際、話し出すときに、「いやいやいや、・・・」(そうではなくて、という意味)という言葉から始めるのです。
この方は若くて非常に優秀です。
事実を把握する力や事実や原因から考えられる対応策の立案力、また判断力などとても優れています。
しかし、社員と話すとき、特に社員が確認や判断を求めていたり、提案をしたりしているときに、ついこの言葉から会話に入ってしまうようでした。
これでは、社員はどうしても相談したり、提案したりすることに躊躇してしまいます。
また、新しいことにチャレンジすることには委縮してしまいます。
頭の回転が速く、すぐに状況を理解し、迅速に適正な対応策を考えたり、正しい判断をできたりする方ほど、どうしても相手の話を否定してしまいがちです。
このような場合、本人は、否定する意識を持っていないことがほとんどです。
このタイプの方は、提案された内容より、自分が考えている内容の方がよりよいのではないのか、と客観的に望ましいアイデアを述べているつもりです。
ところが、これを開口一番言われた方は、度々繰り返されると、「自分はダメなのかな」とつい自分自身を否定的にみてしまいます。
正しいことほど、話し方によっては、相手を傷つけます。
社員の提案に対して感謝の気持ちで返す
これでは社員を自発的人材に育成することはできません。
経営者に社員の提案を否定するつもりはまったくなかったとしても、社員はそう受け取りません。
このような対応になってしまわないように、相談や提案を受けたら、まず、一呼吸置きます。
そして、内容にかかわらず、まず「ありがとう!」と感謝の言葉を返します。
そして、この社員ならではの経験や知識、考えたことの背景に思いを巡らし、「ここがこの提案のいいところだね」などと一度受け止めましょう。
その上で、提案内容によって、「この考え方はどうかな?」と質問形式で返したり、「別の方法は考えられないかな?」と他の選択肢を考えさせたりするようにします。
結論づけて考え方を伝えるのではなく、気づきを与えたり、考えさせるようにボールを投げ返して、対話のキャッチボールになるようにします。
こういった対話の工夫により、結果的に同じことを伝えていたとしても、従来通りの「いやいやいや・・・」と第一声を返答して経営者の正しい考え方を伝えていた時と比べて、会話の後に社員が受ける印象は180度異なっているはずです。
そして社員は、提案が一部認められたことを嬉しく思うとともに、経営者に相談することでより内容がブラッシュアップしたり、自分に足りない部分が明確になったりすることで、「また次も考えて提案しよう」という気持ちになることでしょう。
実は「つい相手の発言を否定してしまう言い方」は、「人より真剣に考えていると自負があり、得意とする分野の話題」では、誰でも無意識にでてしまい、それが普段の「口グセ」や「対話の基本形」になっている場合があります。
もし「社員との対話が上手くいかない」「社員が自分に対して委縮している」という方は、一度身の回りの方とのコミュニケーションを気にしてみたり、ご自身の「口グセ」や「対話の基本形」を振り返ってみたりしてはいかがでしょうか?
きっと周囲とのコミュニにケーションをより円滑にするとともに、「社員の自己肯定感を高める対話方法」の実践につながることでしょう。
(コンサルタント・中小企業診断士 木下岳之)
無料メルマガ登録
専門コラムの他、各種ご案内をお届け中です。ぜひ、ご登録ください。

セミナーのご案内
店舗ビジネスの多店舗展開やのれん分け・FCシステム構築を進めていくため、具体的にどう取り組んでいけばいいのか、どのような点に留意すべきか等を分かりやすく解説する実務セミナーを開催しています。
セミナー一覧ぺージへ