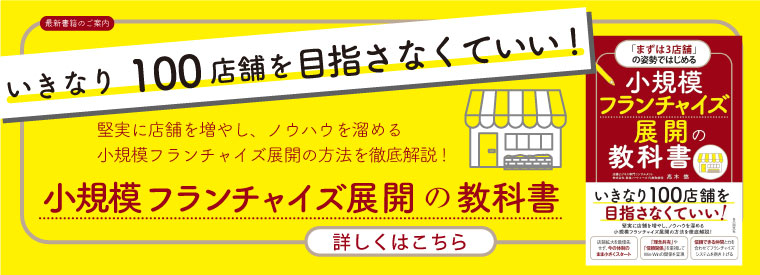ネットラジオ『多店舗化・フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所』は、弊社代表の高木と社労士の田村陽太が、飲食店、整体院、美容院等の様々な店舗ビジネスの「多店舗展開」を加速させるために重要な事を対談形式でお話しするラジオ番組です。
第52回『ネイルサロンを経営しています。のれん分け制度を導入しようと考えていますが、ロイヤリティを払ってまで利用者があらわれるか心配です。どのように進めていくべきでしょうか。』というテーマで店舗ビジネス専門コンサルタントの髙木悠が熱く語ります。
【ハイライト】
・ロイヤリティの本来の目的とは?
・独立者がのれん分けしたくなる仕組みを作るには?
・独立する際に独立者がネックになる「3つの悩み」について
・経営者の意識を発想転換させる重要性
・不十分な自社の経営リソースを補うために大事な事
多店舗化・フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所。この番組は株式会社常進パートナーズの提供でお送りいたします。
店舗ビジネス専門コンサルタントの高木悠が最速・最短で年商30億、店舗数30超を実現する実証されたノウハウをコンセプトにのれん分け制度構築、FC本部立ち上げ、立て直し、人事評価制度の整備など飲食店、整体院、美容院などの様々なビジネスの多店舗展開を加速させるために重要なことを対談形式で分かりやすくお話しする番組です。
田村:こんにちは。パーソナリティーの田村陽太です。配信第52回目となりました。本番組のメインパーソナリティーをご紹介します。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木悠さんです。よろしくお願いします。
高木:よろしくお願いいたします。
田村:高木さん、今日も頑張っていきましょう。
高木:お願いします。
田村:本日のテーマはこちらとなっております。「ネイルサロンを経営しています。のれん分け制度を導入しようと考えていますが、ロイヤリティを払ってまで利用者が現れるか心配です。どのように進めていくべきでしょうか?」ということなのですが、教えてもらってもよろしいでしょうか?
高木:これはあるあるですね。
田村:ロイヤリティ払いたくねえよみたいなことですか。
高木:自分でお店をやったら、不要なコストじゃないですか。田村さんもロイヤリティなんか払ってないわけじゃないですか。
田村:社労士会には払ってないですね(笑)
高木:ネイルサロンで言うと、一般的なロイヤリティの水準で、5%から7%とか、それぐらいは、普通のフランチャイズだったら払うと思うのですよ。だからそれぐらいを独立者は払わなければいけなくなるわけですよね。
田村:はい。
高木:それは普通に考えて、自分がネイルサロンを独自に開業した場合と、のれん分けをして開業した場合で、売上が同じ位しか行かないのだったとしたら、のれん分けは利用しないですよね。
田村;確かにそうですね。自分でやっちゃった方がいいじゃないかなと思いますもんね。
高木:そうそう。でも逆に、売り上げが倍近かったらどうします?
田村:売上が倍いくのだったら、のれん分けしてもらってやろうかなと思いますね。
高木:そうですよね。それで、私こういう考えとか悩み、心配をお持ちの本部経営者の方に守っていただきたい考えというのがあって、それは何かっていうと独立者側の視点に立って、どういう状態になったらロイヤリティを払ってでも、のれん分けしたくなるのだろうかっていう所を考えてみて、必要な仕組みを整えたり、サポート体制を整備していく、これを考えることが大事だと思いますけどね。
田村:なるほど。ちょっと1個質問したいんですけど、加盟者の方が幸せになるイメージを作っていくっていうのは、本部の方の成功体験をもとにイメージしていくのか、どういう風にしてやっていくもんなのですか。
高木:のれん分けを使うっていうことは、独立するってことじゃないですか。それではまず独立者の視点に立って話しますね。独立しようと思う際には、その前には自分で独立するっていう道とのれん分けで独立するっていう二つの道があるわけですね。
田村:そうですね。
高木:普通の人っていうのは自分で独立するっていう道を選ぶわけじゃないですか。だけど、自分で独立するっていう道には、いろんなリスクがあったり、もしくは一歩を踏み出すことに対する悩みや不安があるじゃないですか。
田村:ありますね。
高木:そこで止まってしまっている独立希望のスタッフの方って結構多いと思うんですよ。多いと思うんですよね。それに対し、どんなことが不安に感じているのか、リスクに感じているのか、そこをちゃんと本部が捉えて、そこに対して悩みを解消してあげれば、自力独立ではなくて、のれん分けっていう道を選びませんかっていう事なんですよ。
田村:なるほど。のれん分けしたいっていう方の悩みを解決できるようなソリューションを本部が提供するみたいなことですよね。
高木:そう。例えば、独立者が自分で独立しようかな、のれん分けしようかなって悩むとするじゃないですか。そのときに独立者が感じている悩みとか不安というのは、ほぼほぼもう決まっているんですよ。
田村:はい。
高木:一つ目はお金の問題。「自分で独立してネイルサロンを作りたいんだけど、そもそも初期投資に何百万が必要だけど、そのお金を持ってないのでできません、自分では。」と思っている人がいるんだったら、「うちののれん分けシステムは、本部が作った店舗を貸してあげますから、もう最初は資金を持ってなくても独立できるんですよ」みたいな道が用意されていたら、多少ロイヤリティを払ってでもやろうと思いますよね。自分じゃできないんだからもうそれしか道がないわけじゃないかと思いませんかっていうことなんですよ。
田村:そうですね、嬉しいですよね。のれん分けする方からしたらやっぱり。
高木:そうそう。ただお金の問題って、本部としても負担が大きいじゃないですか。
田村:いやあ、そりゃそうですよね。
高木:だからあんまりサポートしたくないわけですよ。やるにしたって最小限にしたいわけですよ。それ以外の独立者の悩みっていうのを探っていく必要があるじゃないですか。
田村:そうですね。他にはどんな具体的な悩みがあるんですか。
高木:もういくつかしかないんですよ。だいたい独立したいなと思ってるけど、一歩を踏み出せない人が悩んでいることで一番多いのは、お金の次は集客ですよ。
田村:集客ですか。
高木:自分がサロンを作ったけど、思った通りにお客さんは来るのだろうかという心配は絶対あるじゃないですか。
田村:ありますね。
高木:本部はそういう悩みが生じることわかってるわけですよね。のれん分けしたらどうなるんですかって独立者は思うじゃないですか。そこに答えられますかってことが重要なんですよ。
田村:なるほど。確かにそれは大事ですね。
高木:ここも例えばですが、「うちの会社は、この本部の既存店舗を譲りますから安心してください。既存店舗にはもうお客さんこれだけついているから立ち上げたときにお客さんが来ないってことのリスクはないですよ。」と言ってあげるんです。
田村:はい。
高木:「でもそういった価値を提供しているから、ロイヤリティっていうのはやっぱり少し払ってもらわないと、本部も継続できません。どうですか?」って提案をしたらどうですか?
田村:それは不安も払拭されれば嬉しいと思いますね。
高木:そうですよね。それ以外にも、例えば独立者がのれん分けをして新規店舗を出すじゃないですか。その時に本部のホームページには、もう1日何百人とか何千人とかっていう閲覧者が来ているとします。そこに新店舗をオープンしたら、しばらく例えば1ヶ月キャンペーンをやるとして、そういう情報を訴求しますよ、と。
田村:はい。
高木:そしたらその内どれぐらいは、多分予約してくれるよみたいな話があったら、惹かれません?っていうことですよ。自分でお店をやったらそんな集客を期待できないわけじゃないですか。
田村:そうですね。ちゃんと自分たちの悩みについて本部が寄り添っているみたいな感じになりますもんね。
高木:そうですよね。だから、考え方を本部の経営者も変える必要があると思うのですよ。
「ロイヤリティを払ってまで利用者が現れるかな?」っていう不安じゃないですか、これは。でもそうではなくて、ロイヤリティを払ってでも利用したいと思ってもらうために、本部はどうあるべきかっていう話なんですよ。
田村:逆の発想ですね、それはね。ポジティブになっていくべきというか、逆にそれが強みだと本部が言っていくという事ですよね。
高木:そう。そこから逆算していくのが大事です。今お話した通り基本的にはお金の悩み、次は集客の悩み、その次はもう決まっているんですよ。
田村:なんでしょうか、教えてください。
高木:人材の悩みなのですよ。
田村:人材?といいますと?
高木:特にネイルサロンとか、そういう美容系の場合、スタッフを確保する規模感だと人材がそもそも確保できないみたいな悩みがあるんですよね。
田村:美容師さんの資格を持ってるか等の問題もありますよね。
高木:そう。だから、そういう人材が確保できなかったらビジネスが成り立たなくなるじゃないですか。
田村:そうですね。
高木:そこに対しての不安感っていうのも結構大きいわけですよ。
田村:本部としてその際のソリューションとはどのようなソリューションがあるのでしょうか?
高木:例えば、個人ではできない採用活動みたいなものを本部がやっていて、そこに便乗できたりしたら、それってすごいメリットがあるじゃないですか。
田村:確かにそうですね。
高木:例えば学校とかに本部が招かれて説明会をやったりする会社とかってあるじゃないですか。個人規模の会社で絶対そんなところに紛れ込めないわけですよ。
田村:ちょっと資金的にも難しいかもですね。
高木:そうそう。だけどその中に、チェーンの一員としてひっそりと紛れ込んで採用活動を一緒にさせてもらうとか、それ以外にも例えば人材不足が出たときには、本部に余剰人員があるときであれば、本部から社員を出向させますというようなモデルにしてもいいかもしれないですね。
田村:はい。
高木:そうすると、自分で独立したら人がいなかったり、人が辞めてしまったりするとその責任って自分で負わなきゃいけないけど、本部に属していることによって、そういうリスクを回避ができるわけじゃないですか。
田村:そうですね。
高木:そうすると、ロイヤリティを払うのは確かに自分でやっているときに比べて負担なんだけど、それ以上の価値があるかもしれないなって思うかもしれないですよね。そういう仕組みを整えていかないといけないですよ。
田村:なるほど。ありがとうございます。ちょっと1個質問したいのですけども、このネイルサロンの会社さんは、これから第1店舗目ののれん分けを作るみたいな感じだと思うのですよ。
高木:はい。
田村:先ほど高木さんがお金と集客と人材の所のソリューションに対して事前に準備しておくことが大事っていう話があったと思うのですが、これから1店舗目を出すってことは、まだまだその本部の方はもうそこら辺の余裕がない場合もあるじゃないですか。
高木:はい。
田村:つまり代替案というかソリューションがなかなか出しにくい状況もあると思うんですよ。そこら辺をうまい事出していくためのポイントとか考え方を教えていただきたいです。
高木:これはぜひ振り返っていただきたいのですよ。今のままの形を続けたとして、独立者がロイヤリティを払ってでものれん分けしたいと思う状態になるかどうかについてです。
田村:はい。
高木:今の状態でそうなっていなかったら、多分意識せず3年間経営していても問題は解決しないと思うのですよ。だからそこはもうちゃんと意図して作っていかなきゃいけないですよ、今不十分だったら。
田村:なるほど。自然とできていくわけじゃないんですね。
高木:そう。だって今までの経営の結果として今の状態があるわけじゃないですか。そこはのれん分けとか意図しないで経営してきたわけですね。知らないけどそういう状態になってるという事です。普通の会社はそういった状況であると、つまり独立者が現れたときに、「これだったらのれん分け使いたい」と思えるような状況にはなってないんですよ。
田村;はい。
高木:当たり前じゃないですか。のれん分けを想定してないから。でもその状態を続けていたらいつまでたってもなれませんよってことなんですね。だから、今こういうのれん分け制度を入れたいけど、だけどそこに不安があるって思ったじゃないですか。そこが始まりなんですよ。
田村:なるほど、深いですね、これは確かに。
高木:そこで気づいたわけじゃないですか。ではのれん分け制度を利用してもらうためには、うちの会社は何を強化していかなきゃいけないのですかっていうことが、今この瞬間明確になるはずなのですよね。
田村:なるほど。そうすることで経営者も意識し始めると。
高木:そうそう。今日の話を聞いたら、集客面での魅力を出せないかもしれないとか出てくるじゃないですか。でもそれは、意図的に集客面での魅力を作れるように取り組んでいかないと、3年経ってもできないわけですよ。
田村:やっぱり自然とはできていかないものですか。
高木:自然とできてきていたら、多分今の時点で出来ているはずなのですよ(笑)
田村:なるほど(笑)
高木:だからそれは今までの枠組みから外れた活動をしなきゃいけないじゃないですか。だからこのタイミングでのれん分け制度を利用してもらえるようになるためには何が必要かっていうことをちゃんと特定して、そこに向けた一歩一歩を踏み出していく必要があるってことですよね。
田村:なるほど、ありがとうございます。結構時間も近づいてきたんですけれども、高木さんの会社の方でそのような自分たちの会社の本部の強みだったりとか、こういうところってのれん分けの加盟者にPRできるんじゃないかっていうそこら辺の洗い出しみたいなことってしていただけるんですか。
高木:していますよ。だから今お話した通り、ほとんどの会社っていうのは最初の段階では、のれん分け制度をすぐ使いたいと思えるような状況にはないんですよ。だけど、お話をしていると、私達から見ると隠れた魅力って結構あるんですよ。
田村:なるほど。
高木:そういったところをやっぱり探し出して、磨いていく取り組みが、のれん分け制度を使いたいと思ってもらえるようになるためには、すごく重要なのですよね。僕たちというのはそういったのを第三者の観点から見つけて、それをより磨いていくためにどういう風にしていくのかっていうのを一緒に考えるようなお手伝いをさせていただいていますね。
田村:のれん分けをしてみたいけどなかなか自分たちの強みが見つからないっていう企業さんはぜひ常進パートナーズさんに連絡してみたらいいですよね。
高木:はい。そのような本気でのれん分け制度を使って、会社の発展と社員の自己実現を応援したいと考えている会社さんがいたら、我々も本気で対応しますので、おっしゃっていただければと思います。
田村:はい、ありがとうございます。本日はありがとうございました。
高木:ありがとうございました。
無料資料ダウンロード
のれん分け・社員独立FC制度構築の手順やポイントをまとめた資料を無料進呈しています。宜しければ、下記よりダウンロードください。

セミナーのご案内
店舗ビジネスの多店舗展開やのれん分け・FCシステム構築を進めていくため、具体的にどう取り組んでいけばいいのか、どのような点に留意すべきか等を分かりやすく解説する実務セミナーを開催しています。
セミナー一覧ぺージへ