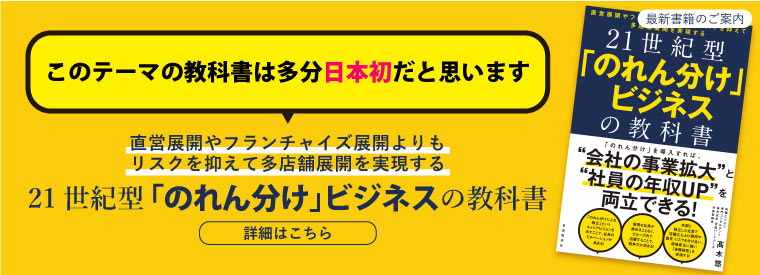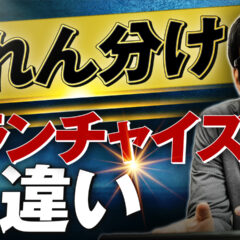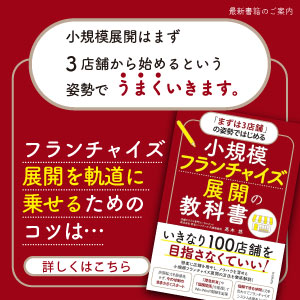ネットラジオ『多店舗化・フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所』は、弊社代表の高木と社労士の田村陽太が、飲食店、整体院、美容院等の様々な店舗ビジネスの「多店舗展開」を加速させるために重要な事を対談形式でお話しするラジオ番組です。
第3回『のれんわけ制度を導入しやすい会社や業種はどんなもの?』というテーマで店舗ビジネス専門コンサルタントの髙木悠が熱く語ります。
【ハイライト】
・のれんわけする上での会社の条件
・繁盛する企業の方程式
・売上を高めるための方法
・従業員にのれんわけ制度を継承する為には?
・自社の強みを探し出すコツ
多店舗化・フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所。この番組は株式会社常進パートナーズの提供でお送りいたします。
店舗ビジネス専門コンサルタントの高木悠が最速・最短で年商30億、店舗数30超を実現する実証されたノウハウをコンセプトにのれん分け制度構築、FC本部立ち上げ、立て直し、人事評価制度の整備など飲食店、整体院、美容院などの様々なビジネスの多店舗展開を加速させるために重要なことを対談形式で分かりやすくお話しする番組です。
田村:こんにちは。パーソナリティーの田村陽太です。配信第3回目となりました。
本番組のメインパーソナリティーをご紹介します。
店舗ビジネス専門コンサルタントの高木悠さんです。よろしくお願いします。
高木:よろしくお願いします。
田村:高木さん、今日は3回目なんですけど、前回はのれん分け制度についてお話させてもらいました。そして、のれん分け制度を導入したいと思う会社さんいろいろあると思うんですが、「のれん分け制度導入しやすい会社や業種にはどんなものがあるのか」ということを、今日はお聞きしたいのですが、どんな業種があるんでしょうか?
高木:まずのれん分け制度を導入できる業種というのはあまり関係無いですね。だから、どんな業種でも導入はできるかなと思っていまして。
田村:そうなんですか?
高木:はい。まずのれん分け制度導入できるかどうか判断の1つのポイントとしては、まず繁盛していることがありますよね。
田村:なるほど。
高木:その従業員さんにそのビジネスモデルを貸して経営させるわけですから、儲かっていないと、そもそも相手が不幸になるじゃないですか。だから、儲かっているということが1つ前提。
その次に大事なことが、その儲かっている理由が明確で且つそれを従業員さんが実行できるようなものになっているかどうか。
これは非常に大事なポイントで、例えばその儲かっている理由が、社長の半端じゃない営業力とかにあるとするじゃないですか。そのノウハウを従業員さんに渡すといっても、半端ない、寝ないで働いているとかだと、そもそもそれできないわけですよ。
田村:無限の体力みたいな。
高木:とか、例えば社長がめちゃくちゃ良い接客をして、その人間味溢れる接客でお客さんがついているとかと言われても、そういう接客できる人とできない人っているわけじゃないですか。だから、そういう系はのれん分けしにくいんですよ。
田村:形が無いものというか。
高木:相手が成功できるかどうかが分からないじゃないですか。
田村:そうですね。
高木:一方で成功している、繁盛している要因が明確な商売、例えば集客はこういうふうにやると一定程度のお客さんは入ってくるとかですね。
あとサービスはこういう流れで提供していくと一定程度の満足が得られるとか、そういう誰でもできるような勝利の方程式みたいなものが、まずあるかどうかですよね。
田村:そこがやっぱり大事なんですね。のれん分けできるかできないかのポイントというか。
高木:やっぱりそこがないとのれん分けってしにくいですよね。
田村:そもそも聞きたいんですけど、繁盛させる仕組みって経営者の方ってどの業種も悩まれていると思うんですけど、高木さんが考えるに経営者が繁盛させられる仕組みづくりって何が1番重要ですか?
高木:繁盛させる仕組みで重要なこと。
田村:いろいろな業種あると思うんですけど、こういう会社は繁盛しているなとか、やっぱりそれだけ繁盛させるだけをした方程式がしっかりしていれば従業員さんにも独立してもらう時もちゃんと教えられるじゃないですか。
その方程式ってどの経営者も作るのにたぶん困っていると思うんですよ。何が1番大事なんですか?
高木:今の時代でいくとどんな商売でも競争ってあるじゃないですか。例えば美容院の例でいくと唯一無二のカットができる美容室で、いわゆるそのカリスマ美容師だけで。
田村:一時期流行りましたね。
高木:それを除けば基本的にカットするということだけでは差別化ってできないわけですよ。だから、それ以外でやっぱり差別化するポイントを持っていないといけないですね。
田村:と言いますと、例えば美容院だと具体的にどういうところで差別化するというか。
高木:例えばお客さんが来てくださって、そのお客さんにこのお店また来たいなと思ってもらえるような何かがないといけないわけですよ。
田村:そうですね。
高木:でもカットでは差別化しにくいわけじゃないですか。例えばそのお客様が帰っていった後に今日は来てくれてありがとうございましたみたいなお手紙が届いたとしたら、これって、本質的なサービスではないんですけど他社と差別化するという意味では1つのポイントになるというか、記憶に残ったりするわけじゃないですか。
田村:そうですね。
高木:お客さんとの関係作りという観点であれば1つありますね。
田村:なるほど。そうやっていろいろ取り組んでいくじゃないですか。
次またもう1つ質問なんですけど、売り上げという結果に繋がるところ、繋げるためにはどれくらいの努力というか、どんなところを頑張っていけばその取り組みが結果に繋がるものなんですか?
高木:2つの軸で取り組んでいく必要があるかなと思っていまして、まずは基本的にその商売繁盛させるためには新規のお客さんを取って、そしてその新規のお客さんをリピートさせるということが大切じゃないですか。
私よくバケツで例えるんですけど、バケツの中に入っている水がお客さんの数であり売り上げなわけですよ。そのバケツの水を増やしたら売り上げ上がるわけですよね。
田村:そうですね。
高木:当然その中に水を注ぐじゃないですか。これは新規のお客さんを取るための方法ですよね。
でも大体バケツって穴が空いているわけです。例えば不満足だったらお客さんは二度と来ないですし、引っ越したり例えば学生が就職したりしたら来なくなるじゃないですか。
だから、バケツって絶対穴が開いているんですよね。そこの穴をちゃんと塞いでおかないと新規でお水を入れてもどんどん減っていっちゃうわけですよ。
田村:なるほど。
高木:だから、その新規のお客さんを取るというのと、やっぱりその取ったお客さんをリピートさせるという、その2つの軸で取り組む必要があって、新規のお客さんを取る方法っていろいろあるんですけど、ここで大事なことというのは他人の土俵に乗るのではなくて自分達でコントロール可能な取り組みで売り上げを作る。
例えばこれ飲食店でいくと食べログとかにお金を払って載せたりするじゃないですか。それで売り上げが上がったりすると思うんですよ。これって要は他人の土俵なわけですよね。そのサービスの仕様変更があったりしたらやっぱり売り上げ落ちたりするでしょうし、もしくはそもそもそのサービスが無くなったりしたら、売り上げそこから取れなくなっちゃうじゃないですか。
田村:メニューも見えなくなっちゃいますもんね。
高木:そうそう。だけど、例えば自分たちがブログ書いて、そこから新規のお客さんを取っているとか、チラシ配りとかでも良いんでしょうけど、自分達でお客さんを開拓するまでのツールを持っていれば、自分たちがコントールできるわけですよね。
田村:そうですね。
高木:だから、そういった観点で新規のお客さんをどう取っていくかを考えなきゃいけないと。
田村:やっぱり自分達にしかできないサービスというのは何かということを考え続けるというか。
高木:そうですね。だから、自分達でコントロールできる方法を考えていく。で、来てもらったらリピートしてもらうわけですよ。
リピートしてもらうために大切なことというのは、やっぱりこっちから情報発信できるような体制を作っていく。リピート対策というと例えばさっきの飲食店でいうと、お会計の時に割引券配ったりスタンプカード配ったりしてまた次使ってもらうと。
それでも良いんですけど、割引券とかスタンプカードとかって、それを使うかどうか思い出してもらうかどうかってお客さんに委ねられるわけですよ。
田村:確かにそうですね。
高木:財布の中に入れられて思い出してもらえるかどうかって分からないじゃないですか。
田村:そうですね。
高木:だから、結構コントロールがしにくいんですね。
田村:意外にそうなんですね。
高木:その点、例えばLINEに登録してもらうとか、さっきお話しした手紙を送るとかは、こちらの意図したタイミングでお客さんに情報を届けられるじゃないですか。
田村:そうですね。
高木:なので、そのリピートさせるという観点でいくと、やっぱりこちらから能動的に情報発信できるような何かツールを備えておくと、計画的に売り上げが作れますよね。
田村:そうですね。
高木:だから、その2つの軸で作っていくと集客なんか安定していくと思いますけどね。
田村:今めっちゃ良いこと聞きました。ありがとうございます。こういう勝利の方程式というか売り上げの方程式がしっかりできている会社というのが、のれん分けに最適な会社だと思うんですけど、また質問に戻るんですけど、そういうのれん分けを従業員さんにやっぱりその勝利の方程式というのは受け継いでいくわけじゃないですか。そこへのポイントって何かあるんですか?その先のポイントというか。
高木:やっぱりそれを紙とか明確に見えるものに落とし込むということでしょうね。
田村:と言いますと?
高き:私もこういう仕事をしているので、フランチャイズ展開する時とかのれん分けシステムをする時になんで繁盛しているんですか?と聞くんですよ。そうすると経営者によって返ってくる答えにかなり差があるなと思っていて、すごい具体的にそれが説明できる経営者もいるんですけど、それがなんともふやふやとしている経営者もいらっしゃるんですよ。ふやふやとしている経営者のほうは、経営者以外の他の従業員さんとかに聞いたりするとまた違った答えが返ってきたりするんですね。それは基本的に統一できていないわけですよ。
田村:そうですね。
高木:だから、それではやっぱりダメで、うちが勝っているのはこういうことなんだということをやっぱり明確にしなきゃいけなくて、そのためには紙に落とし込んでいく。
そういうものじゃないと基本的に紙に落とせないものって整理できていないものですから、だからまずは1回紙に書き出してみて勝つためのポイントというのを明らかにしていく。それがスタートですね。
田村:じゃあよく経営者の方が成功した秘訣なんですか?と言われて、やっぱりその時のご縁かな、みたいなそういう漠然としたものは紙に落とせないですもんね。
高木:そのままだとのれん分けはしにくいですよね。
田村:なるほど。そこ紙に落とすということが大事なんですね。
高木:大事ですね。
田村:書き出す時にやっぱり難しいと思うんですよ。やっぱりなんとなくは分かるんだけど具体的に書くとなると難しいと思うんですけど、どういうとこを意識したいったらいいですか?そのポイント。うちの勝利の方程式は何だって紙に落とす時って、何を振り返っていったらいいんですか?
高木:でもこれは慣れていないとやっぱり難しいんですけど、良くないのはあまり難しく考えすぎて紙に書かないこと。それじゃダメで、とにかくなんで勝っているんだろうなって考えたら、思いついたものをまずとにかく適当に書き出す。
適当に書き出していってみて、もう書けないというくらいまで書くんですよ。そしたら同じようなこと書いてあったりするじゃないですか。似たようなこと書いてあったり。
そういうのをちゃんと整理していくわけですよね、グルーピングしていって。その作業をしていると不思議なものでちゃんと整理されていくんですよ。
これ1番ダメなのが、頭の中で考えていること。頭の中でグルグル回っておしまいですから、これ騙されたと思って書いてグルーピング。また思いついたら書いてそれをグルーピング。これを繰り返すだけでほとんど整理できると思いますけどね。
田村:その整理されるってどんな感覚で整理されるんですか?あっこれは綺麗に収まったって、うちのポイントはこれだっていうのが分かるんですか?
高木:やっぱりそういった書き出してグルーピングということをやっていくと、何個かに絞られていくわけですよ。いろいろな要素があるんですけど、似たようなものを1つのグループにまとめていくと、結局残るのっていくつかになっていくんですね。
いくつかのグループになっていく。そこまでいったらほとんど整理できているわけですよね。その中にあるものからうちが成功するために何を守らなければいけないのか、どうすべきなのかというところが、シンプルな文章になって整理できてくる。
田村:それがやっぱりのれん分けする従業員さんにとっても、こういうところが会社のポイントだからそれはやっぱりのれん分けをする際にも重要になってくると。
高木:そうですよね。やっぱりそういうのが無いと結局もう成功できるかどうかって従業員さん次第になっちゃうじゃないですか。
田村:そうですね。怖いですよね、独立して。
高木:従業員さんから見たら、これを頑張れば良いんだという状態だったら分かりやすいですよね。
田村:そうですね。
高木:なので、そういった状態までしていかないとのれん分けってできないんですけど、逆に言うとそれができていれば基本的にはのれん分けできる。
田村:なるほど。ありがとうございます。今日はのれん分けをしやすい業種や会社ということでお聞きして、すごい良いポイントを教えてもらいました。ありがとうございます。最後に何か一言ありますでしょうか?付け加えは大丈夫ですか?
高木:もっとのれん分け制度を導入しやすい会社とか業種のポイントってたくさんあるので、またこれは追々お話をさせていただきます。
田村:分かりました。ありがとうございます。それでは高木さん、今日もありがとうございました。
高木:はい、ありがとうございました。
無料資料ダウンロード
のれん分け・社員独立FC制度構築の手順やポイントをまとめた資料を無料進呈しています。宜しければ、下記よりダウンロードください。

セミナーのご案内
店舗ビジネスの多店舗展開やのれん分け・FCシステム構築を進めていくため、具体的にどう取り組んでいけばいいのか、どのような点に留意すべきか等を分かりやすく解説する実務セミナーを開催しています。
セミナー一覧ぺージへ