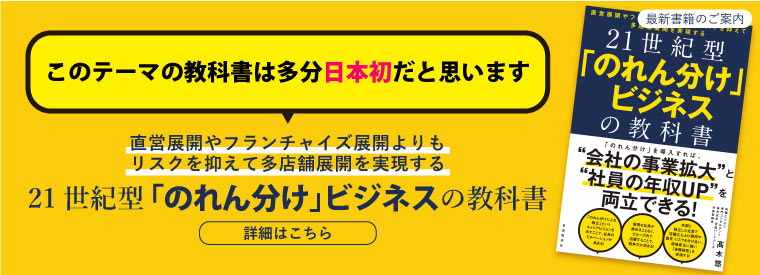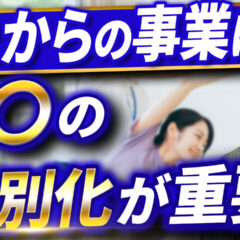優良企業には緻密な制度と運用がある事実
先日、倒産寸前の企業を27年連続黒字企業に再生させた、ある中小企業経営者の方のお話を聞く機会がありました。
社員をとても大切にする会社として有名であり、「経営は社員満足第一、絶対に雇用は守る」と言い切られた時には、「ぶら下がる社員は出てこないのかな…」とふと思ったものです。
しかし話を聞いていくうちに、社員を大切にすることは決して甘やかすことではないことがわかりました。
具体的には、社員の働き方の実態や要望に合わせて、柔軟に人事制度に変更を加え、解雇はしないことで雇用面での安心感は与えるものの、業績面での結果と態度・能力の成長を常に求め続ける評価制度を構築し、さらに本人が納得するまで面談を行う、丁寧な運用をしているのです。
例えば就業規則はこれまですでに25回改訂し、評価制度は本人が直属の上司面談だけでは納得しない場合、社長も対応する(しかも複数回)こともあったそうです。
つまり「その人が何らかの理由で力を発揮できない状況があった場合、会社の制度変更で対応できる障害は取り除き、そのうえで本人に対し会社が望む成果や成長を明示し、行動の結果を本人も納得する評価でフィードバックしている」ということです。
そこには「ぶらさがり」という甘えはなく、「会社の一員として、今の自分ができること、期待されていることをやり切ろう」という強烈な自責主義が会社の中に貫かれていました。
制度は作るより運用が難しい
このお話を聞いたときに思い出したのは「評価制度はあるのですが、最近、運用をやめています」というある企業の経営幹部の方々です。
なぜ運用をやめているかをお聞きすると「直属の上司がつけた評価と社長がつけた評価が違った」からだそうです。
もちろんそういった状況はどこの企業でもあります。
実際には上位評価者の評価が、最終評価になるのが一般的です。
しかしどうやらその企業では、評価者間の話し合いもなく、真逆に近い社長の評価が採用され、人事担当者や一次考課者である直属の上司は「何のための評価制度なのか」という気持ちになり、社長も「うちの会社に評価制度は意味がない」と判断されたようでした。
評価制度における経営者というブラックボックスの存在
多くの経営者は、社員への期待と成果を明らかにし、頑張った人が認められる会社にすることで、これまで以上に社員に自律的に働いてほしいと思い、制度を整えたことでしょう。
しかし日々の忙しさに翻弄され、「制度は作ったから、あとは人事担当を中心に運用して」ということになっていないでしょうか。
もしくはそもそも「人事担当が中心に作った制度であり、社員のことは自分が一番わかっている」という「経営者は治外法権」スタンスで、自社の制度に相対していないでしょうか。
一般的に評価制度の運用は、「目標の設定と実行、期中・期末の面談、上司による評価、評価者会議、本人へのフィードバック」が一連の流れですが、運用がうまくいっていない企業では、この「評価者会議」が行われずに、上司評価の後に「経営者評価」というブラックボックスへ入れられて、結果をフィードバック、もしくはフィードバックもなく決定、という流れになっているようです。
大切なのは経営者とほかの評価者の目線合わせ
なので「運用がうまくいっていない」という経営者の方は、まずは「評価者の目線合わせ」をやっているか、もしくはやっていても「機能しているか」を、ご確認いただきたいと思います。
なぜなら評価制度は、評価者の教育が最も難しいといわれるからです。
しかも中小企業は、経営者の個性で業績を伸ばしてきた企業も多く、杓子定規に制度を運用することが、会社の実情に合わないことも多々あります。
実際に「社長の評価が一番正しい」というのは、真実に近いとも言えます。
社長は「会社の理念やビジョン」に基づいた会社の目指すべき方向性に、その社員の行動が合致しているとき、行動や成果を評価しているはずです。
ではなぜ他の評価者は、社長と同じように正しく評価できないのでしょう。
それは「社長が評価する基準」が評価者に伝わっていないからではないでしょうか。
なので、ご自身の判断基準を言葉にして、社員と共有していただきたいのです。
どんな行動や成果を評価するのか、しないのか、その目線合わせが「評価者会議」の目的です。
そして経営者の頭の中にある「評価に関するブラックボックス」の中身を、社員と共有し、さらにその「評価基準」を、評価制度の項目へ反映していただきたいと思います。
その結果、社長が評価する行動や成果が、評価を受ける社員にも評価者にも明らかになり、評価制度を運用することで、会社全体が「会社の理念・ビジョンの実現」へ近づく第一歩となるのです。
無料メルマガ登録
専門コラムの他、各種ご案内をお届け中です。ぜひ、ご登録ください。

セミナーのご案内
店舗ビジネスの多店舗展開やのれん分け・FCシステム構築を進めていくため、具体的にどう取り組んでいけばいいのか、どのような点に留意すべきか等を分かりやすく解説する実務セミナーを開催しています。
セミナー一覧ぺージへ