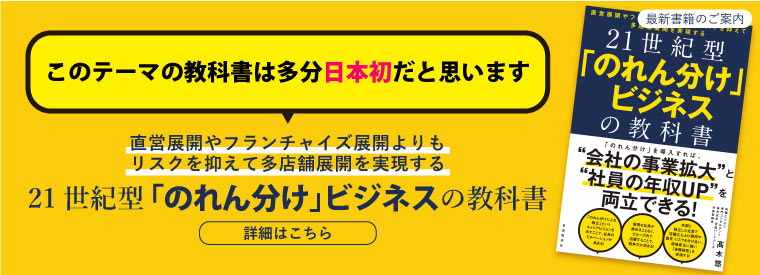先日独立行政法人労働政策研究・研修機構の人材育成と能力開発に関する興味深い調査結果がありました。
それによると約7割の企業が、社員に人材育成方針が浸透しているというのです。
規模別にみると、規模の小さい企業ほど「浸透している」とする回答割合が高かったそうです。
今後は少子化もいっそう深刻になり、人材一人ひとりの重要性が高まるとともに、社員を自発的人材に育成することが重要です。
そこで、上記の調査結果を踏まえ、社員を自発的人材に育成するための3つのステップをご紹介します。
なお、店舗ビジネスのキャリアの限界を突破する「のれん分け制度」づくりや成功のポイントを知りたい方はこちらのコラムをご覧ください。
人材育成方針を浸透させている企業は約7割
先日独立行政法人労働政策研究・研修機構の人材育成と能力開発に関する興味深い調査結果がありました。
それによると、社員に人材育成方針がどのくらい浸透しているかを尋ねた質問では、「浸透している」が7.2%、「ある程度浸透している」が66.3%、「あまり浸透していない」が24.4%、「浸透していない」が1.4%で、7 割以上が浸透していると回答していました。
規模別にみると、規模の小さい企業ほど「浸透している」とする回答割合が高かったそうです。
人材育成方針を定めていない企業が約3割
また、人材育成・能力開発の方針を尋ねたところ、「今いる人材を前提にその能力をもう一段アップできるよう能力開発を行っている」企業の割合が30.9%で最も高い結果でした。
しかしながら、実は「人材育成・能力開発の方針について特に定めていない」が26.8%で2番目でした。
次いで「個々の従業員が当面の仕事をこなすために必要な能力を身につけることを目的に能力開発を行っている」(22.3%)、「数年先の事業展開を考慮して、その時必要となる人材を想定しながら能力開発を行っている」(10.4%)と続きました。
つまり、人材育成方針を策定している企業の多くはそれを浸透させているが、「人材育成方針を定めていない企業」が約3割にも上っていました。
この結果は少々残念でした。
本コラムを通じて、自発的人材育成の重要性を述べ、そのためには人材育成方針を策定して公表・浸透されることが大切であることをお伝えしてきているからです。
規模別で見てみると、規模の小さい企業ほど方針を定めていない傾向にありました。
規模が小さい企業は方針策定まで手が回らないのかもしれませんが、策定できれば浸透しやすいという調査結果がでていますので、しっかり人材育成方針を定めることが必要です。
約8割の企業がOJTを教育訓練として重視している
そして、重視する教育訓練については、約8 割(82.1%)の企業がOJT(職場での実務に基づく教育訓練)を、OFF-JT(研修など従業員の能力開発・向上を図るため、業務命令に基づき通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練)よりも重視していました。
OFF-JTを重視する企業は、11.5%と少なかったようです。
社員を自発的人材に育成するための3つのステップとは
不確実性が高まった現代では、これまでに直面したことがないような新しい問題に対処していく必要があります。
成熟した社会では、技術の発展とともに顧客はそのベネフィットを享受しようとするため、顧客の志向は刻々と変わり、パーソナライズ化や詳細化、多様化がますます進みます。
また、少子化はいっそう深刻になり、近年にないくらいの賃金の上昇圧力が発生するかもしれず、人材一人ひとりの重要性が高まります。
そのため、このような社会環境においては、社員を自発的人材に育成することが重要です。
そこで、上記の調査結果を踏まえ、社員を自発的人材に育成するためのステップを改めてご紹介します。
人材育成方針を策定する
人材育成のはじめの一歩は人材育成方針の策定です。
人材の重要性がより高まった現代では、人材育成をしっかり経営方針と整合させ、会社の重要な施策の1つとして捉えることが必要です。
会社の経営理念や経営方針を実現させるのは社員であり、そのために、社員にどのような人材になってほしいのか、どのような人材育成策を実施するのかを表現するものが、人材育成方針です。
筆者は、人材育成の最終ゴールは、人材を自発的人材に育成することであると考えます。
もちろん、社員が当面の業務を実行できるように実務能力を身につけさせることは重要ですが、それだけでは短期的な人材育成です。
もう少し長期的な視点で、社員のスキルのレベルアップや多様化を図るとともに、社員を自ら進んで考え自発的に行動できるようにすることが、会社を持続的成長へと導きます。
人材育成方針を浸透させる
そして、策定した人材育成方針や施策は、社内外に公表し浸透させます。
本気で社員に成長してほしいと期待するのであれば、まず会社が社内外に人材育成を進めることを約束する必要があります。
人材育成には時間がかかりますし、コストや手間も発生します。
会社としてこれらにオープンに対処してこそ、その本気度が社員や求職している人に伝わり、彼らを動機づけます。
また、会社が期待している人材像を明確にすることで、社員がその人材像を目指しながら成長します。
問題解決させる考え方、手法を身につけさせる
人材育成というと当面の業務を実行できるようにさせたり、社員の能力を高めたりすることに注力しがちで人材育成施策がOJTに偏りやすくなります。
OJTは必須な教育訓練の1つであり、業務に慣れることができるようになります。
しかし、そればかりでは長期的な成長は望めません。
現代において、会社に求められていることの本質は、製品を作ったり売ったりすることではなく、顧客の問題を解決することであると言われます。
例えば、都心にある雰囲気のよいレストランは大切な人と何かを祝うのに適しているでしょうし、駅前にある牛丼屋は安くて早くておいしい牛丼を提供し会社員や学生を満足させます。
どちらも食事を提供する飲食店ですが、ただ食事を提供するのではなく、ターゲットとする顧客の課題を解決しているのです。
会社が問題解決を求められているということは、社員一人ひとりが戦力として、問題を解決できるようになる必要があります。
そのためには、OJTだけに頼るのではなく、社員が多様な考え方を持ち、新しい問題解決手法を身につけられるように、外部の研修を受けさせたり、社内の他の店舗と交流させたり、プロジェクトに参画させたり、業界団体のイベントに参加させたりするなど、社員が成長できる機会を提供することを心がけることです。
これらにより、社員が通常の業務の枠を超え、新しい気づきを得て、自発的に行動できる人材へと近づきます。
このように、会社の将来を背負って立つ自発的人材を育成するには、人材育成方針を策定して浸透させ、社員に問題解決させる考え方、手法を身につけさせることの一連の流れが必要です。
人材育成が大切だと認識しても、目標を設定していなかったり、OJTや研修の機会を計画もなしに提供するだけでは、社員は会社が求める自発的人材には成長しません。
会社が強い意思を持って、経営方針と一貫した人材育成に計画的に取り組むことが必要です。
(コンサルタント・中小企業診断士 木下岳之)
無料メルマガ登録
専門コラムの他、各種ご案内をお届け中です。ぜひ、ご登録ください。

セミナーのご案内
店舗ビジネスの多店舗展開やのれん分け・FCシステム構築を進めていくため、具体的にどう取り組んでいけばいいのか、どのような点に留意すべきか等を分かりやすく解説する実務セミナーを開催しています。
セミナー一覧ぺージへ