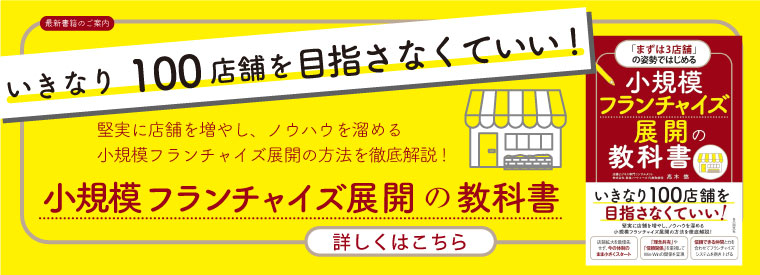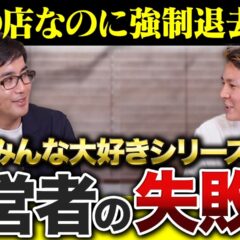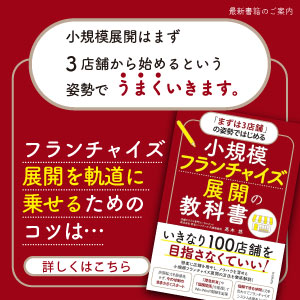質問するということは、部下との対話に限らず多くのコミュニケーションにおいてとても大切な行為です。
質問を考えるということは、そもそも何を問題として捉えているのか、を意味するからです。
質問することは部下に対してメッセージを送ることであり、これが部下との距離を短くし人間関係をスムーズにします。
そこで、部下を前向きにさせる効果的な質問方法と上達の仕方についてご紹介します。
なお、店舗ビジネスのキャリアの限界を突破する「のれん分け制度」づくりや成功のポイントを知りたい方はこちらのコラムをご覧ください。
コンテンツ
(1)人材育成に力をいれる経営者が増えてきた
最近人材育成に力を入れる経営者の方が増えてきたように思います。
何人かの経営者の方とお話をしても、コロナ禍での今後の市場や顧客動向に加えて、人材について注目する方が増えてきました。
この2年以上にわたるコロナウィルスの影響は一時的なものではなく人々の思考や行動を大きく変えてしまいました。
もう以前とまったく同じ社会に戻ることはないでしょう。
この変わってしまった社会のなかでどうやって生きていくのか、どうやって会社を経営して成長させていくかを考えなければなりません。
それには、多様な意見を聞き試行錯誤することが求められ、そのために自発的に行動できる社員を1人でも多くすることが必要です。
社員が自発的に行動できれば、仕事や店舗を任せることができ、さらに、これからどのように市場や顧客にアプローチするのか、どのような商品やサービスをどうやって提供するのかなど、会社が進むべき方向性や取るべき対応策を見つけやすくなります。
(2)社員を自発的に行動させるために質問を活用する
社員が自発的に行動するとは、自ら考えたことに従い自主的に動くことです。
上司などからの指示や命令で動くことではありません。
つまり、社員が自ら行動できるように育成することが必要です。
しかし、これは簡単なことではありません。
受け身的にどうしても指示を待ってしまう社員がいるものです。
このような社員の多くは、自発的に考え行動するということが習慣化されていないからできないのです。そこで、社員との対話のなかで質問を活用して、社員に考え行動させることを意識づけするようにします。
このような対話を習慣的に行うことで、少しずつ社員が変わってきます。
(3)質問により部下に関心があることを示す
質問するということは、部下との対話に限らず多くのコミュニケーションにおいてとても大切な行為です。
質問を考えるということは、そもそも何を問題として捉えているのか、を意味するからです。
仕事は学校の授業ではありませんから、予め解答が決まった問題がでるわけではありません。
業務のなかで課題を発見しなければなりません。
何を問題として認識するかであり、問題をしっかり見極められれば、より早く適切に対処できます。
逆に間違えてしまえばいつになっても問題が解決されません。
多くの方がよく質問する際に慎重になりますが、それはこの表れと思います。
質問することは、問題意識を表明することです。
そして、対話では、質問することは話す相手(部下)に対して関心を持っていることを示します。
質問することは部下に対してメッセージを送ることであり、これが部下との距離を短くし人間関係をスムーズにします。
しかし、対話において相手が一方的に話してばかりいることを経験したことはありませんか?
どのように感じましたか?
内容にもよりますが、相手の関心は話しかけられている自分ではなくて、話している人自身にあると感じるものです。
そうならないように、上司からしっかり関心を示すことで、関心を示された部下は信頼感を抱き、質問に対して回答するために考えるようになります。
そして、考えを言葉にしようとすると頭の中が整理されます。言葉にすることで自分の考えに気づくのです。
(4)部下を前向きにさせる効果的な質問方法とは
質問を効果的に活用すれば、このような大きな効果が期待でき、部下をやる気にさせることができます。
しかし、慣れていないと、問い詰められたり責められたりしているように部下に感じさせてしまう場合があります。
例えば、「なぜこのやり方をしたの?」といった質問です。
「なぜ?」と尋ねると「なぜこんなことをしたのか?」と反語的な意味合いを感じさせてしまう場合があります。
特に部下の場合は、上司との対話に身構えてしまい、考えを発したりせず消極的になってしまいます。
そこで、留意したいポイントは、ある問題点を話題にするときには、過去や現在の判断や行動の理由を直接質問しないことです。
その代わりに、「これをやると(やらないと)どうなると思う?」と将来について質問することです。
この少しの工夫により、責められている感じがなくなり、前向きに問題点を捉えることができるようになります。
また、「どのような作業手順か教えて?」などと知識だけを問わないことです。
答えられれば部下は安心するかもしれませんが、それは部下が自分の頭で考えた答えではなく、覚えていたものでしょう。
それよりは「作業で改善するところはあるかな?」など、部下の考えを引き出すような質問にします。
同じことを質問していたとしてもその質問の仕方で、部下の捉え方がまったく異なります。
(5)日頃から周囲の質問を意識して質問の仕方を磨く
効果的な質問方法は誰でもはじめからできるものではありません。
質問が上手になるためには、いくつかの工夫が必要です。
経営者や上司の方でも、日頃の対話のなかで質問されることは多くあると思います。
それらの質問を振り返り、どのような質問だと答えやすかったか、ネガティブに感じたのはどのような質問だったか、などと思い出してみます。
回答を引き出す上手な質問は今後使えるようにし、そうでない質問は他山の石として役立てます。
また、質問が上手な方を見つけたら、マネをしてみます。
慣れないうちは、上手な質問のマネをすることが上達の早道です。
このように、質問の仕方について日頃から意識をすることで、部下をやる気にさせる効果的な対話ができるようになります。
(コンサルタント・中小企業診断士 木下岳之)
無料メルマガ登録
専門コラムの他、各種ご案内をお届け中です。ぜひ、ご登録ください。

セミナーのご案内
店舗ビジネスの多店舗展開やのれん分け・FCシステム構築を進めていくため、具体的にどう取り組んでいけばいいのか、どのような点に留意すべきか等を分かりやすく解説する実務セミナーを開催しています。
セミナー一覧ぺージへ