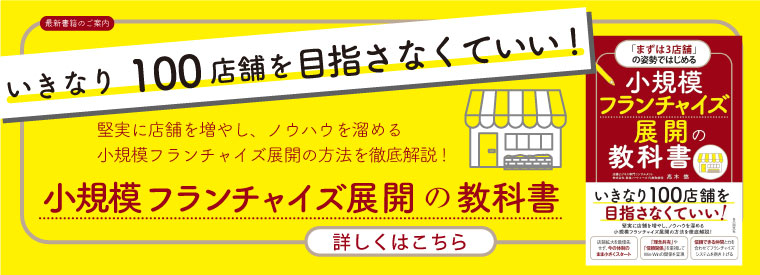諸説あると思いますが、のれん(暖簾)分け制度は江戸時代から始まったと言われています。
現代の「のれん分け制度」とは似て非なるものがあり、表層的には同じように映りますが深層的には概念が異なる部分もあります。
今回は江戸時代版を「暖簾分け」、現代版を「のれん分け」と定義して、違いを考察してみたいと思います。
なお、店舗ビジネスのキャリアの限界を突破する「のれん分け制度」づくりや成功のポイントを知りたい方はこちらのコラムをご覧ください。
江戸時代の「暖簾分け制度」
この時代の暖簾は店の信用・信頼・格式といった意味があります。
そこに家紋や屋号がついています。現代企業ではロゴや企業ブランドと言えるものです。
暖簾分けが認められるのは、長年奉公した“番頭”や“手代”と言われる人たちです。
彼らは営業に関して“仕入れ“や“販売“などの重要業務を任され、代理権と言えるほどの高度な権限を本家から与えられ者たちです。
高いレベルで意思決定ができる者にのみ別家が許され、本家の屋号を使い、本家の仕入れ先や伝手を使って商売ができるのがこの時代の「暖簾分け」です。
加えて、長年の報酬として独立資金や経営危機の際の援助も受けていました。
現代版の退職金制度と言えるでしょう。
逆に「暖簾分け」で独立した後も、資金援助と引き換えに本家への奉公は継続しており、双方の信頼関係のもと、信用・信頼・格式を維持してきたのです。
現代版の「のれん分け制度」
現代の「のれん分け制度」は次の意味合いがあります。
①店舗数拡大を加速させる目的
②社員のキャリアアップとして独立制度を準備し、会社の働く場としての魅力を高める目的
これには経済成長を前提とした資本主義社会と、個人の働き方やキャリアパスの考え方が背景にあります。
江戸時代の「暖簾分け制度」と最も大きな違いはここにあり、「信用・信頼・格式」といった部分はやや希薄化している印象です。
この違いは良し悪しではなく、時代に合った制度へ変化させることは正しい選択と言えます。
しかし昔の「暖簾分け制度」の良いところ、大事にしてきた点も取り入れなければ勿体無いとも言えます。
現代版「のれん分け制度」の課題解決 ①人材育成
店舗数の拡大を事業目標にした企業が必ず直面する課題は人材育成が追いつかない事態です。
新しい箱(店舗)を作っても、その店舗を運営する人材が育っていなければ競争力はたちまち失います。
ブランド力の毀損すら招きます。
従って、店舗数拡大や「のれん分け制度」を整備するのと同じレベルで、人材育成システムも整備しなければならないのです。
これは単なる“教育プログラム”や“研修制度”を整備することに留まりません。
自然と人材が育成されていく社内マインドの醸成です。
このマインドは経営者(社長)の思想が大きく影響します。
有名な人材育成企業の例として、リクルート・セブンイレブン・マクドナルドやグローバルに展開するコンサルティング会社があります。
ここの出身者は独立して多方面で活躍している方々が非常に多いのが特徴です。
これらの企業は、自分の頭で考えて自分の意思で行動し、責任の所在も明確にしています。
働く社員も独立することが当たり前(前提)のマインドで働いています。
退職者の数も多いですが、新しい人材も次々と入社しては育っていきます。
日本で少子高齢化社会になったとしても、こういった企業には人材不足には陥らないのです。
新陳代謝の重要さを肌で感じて、実践しているのです。
現代版「のれん分け制度」の課題解決 ②明確な制度設計
先程、「信用・信頼・格式」の希薄化について触れましたが、家長制度や家督制度の概念が薄くなったと同じくして、現代社会では精神的な信頼関係だけで格式を守ることはできません。
しかし「信用・信頼・格式」を制度の運用で補うことはできるでしょう。
独立「のれん分け制度」の設計と社内への明示
入社時から「のれん分け」の制度設計を詳細に社員に明示することです。
①のれん分け制度」を利用する条件
② 最短何年で独立できるのか
③「のれん分け制度」の利用メリット
利用条件を明確に示した上で、ブランド力を守れるレベルに達していない社員に対しても丁寧に説明し、独立レベルに達するまで教育する気概も経営者には必要となります。
「のれん分け制度」の契約書を整備する
本家に奉公し続ける昔の「暖簾分け制度」とは違い、民主主義が進化した今の時代は個人が尊重されます。
しかし、「信用・信頼・格式」を包含した“ブランド力”の維持は重要な課題です。
そのためにはフランチャイズ契約と同様に、明確に「のれん分け制度」の契約書において互いの約束事を決めておくことが賢明です。
まとめ
「暖簾分け制度」と「のれん分け制度」の違いについて触れてきましたが、精神的に信頼関係で成り立っている事に違いはありません。
時代に合った思想で制度設計と運用で信頼関係を維持するのです。
現代版「のれん分け制度」は、同じ釜の飯を食べた仲間が独立しても、同じブランド内(グループ内)で一緒に成長していく姿を共有できる、現代版の心地よい絶妙な人間関係を表現できるいい制度と言えるのではないでしょうか。
無料資料ダウンロード
のれん分け・社員独立FC制度構築の手順やポイントをまとめた資料を無料進呈しています。宜しければ、下記よりダウンロードください。

セミナーのご案内
店舗ビジネスの多店舗展開やのれん分け・FCシステム構築を進めていくため、具体的にどう取り組んでいけばいいのか、どのような点に留意すべきか等を分かりやすく解説する実務セミナーを開催しています。
セミナー一覧ぺージへ