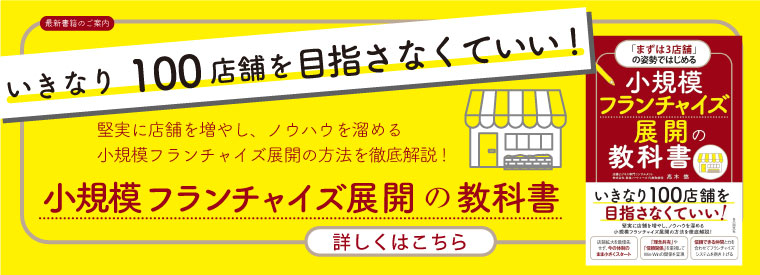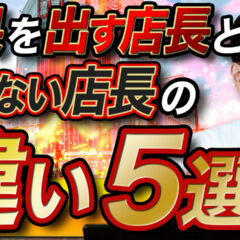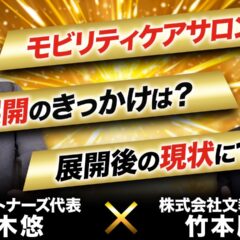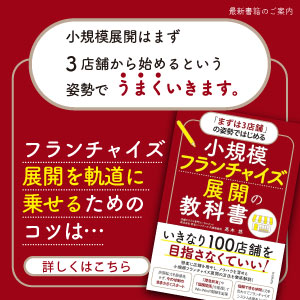ネットラジオ『多店舗化・フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所』は、弊社代表の高木と社労士の田村陽太が、飲食店、整体院、美容院等の様々な店舗ビジネスの「多店舗展開」を加速させるために重要な事を対談形式でお話しするラジオ番組です。
第67回 『整体院を2店舗経営しています。今後、30店舗展開を目標にしています。多店舗化に成功している企業の特徴を教えてください。』というテーマで店舗ビジネス専門コンサルタントの髙木悠が熱く語ります。
【ハイライト】
・売上が伸びている会社と伸び悩んでいる会社の違いとは?
・経営計画発表会を社内で行う重要性
・経営計画発表会はどのようなプログラムを企画すれば良い?
・明確な社内目標を公表する事で会社にもたらす良い影響
・アウトプットはインプットの質を高める事に繋がる
・会社経営に必要な「健全な強制力」
・経営計画発表会で意識すべきは「非日常的な場作り」
多店舗化・フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所。この番組は株式会社常進パートナーズの提供でお送りいたします。
店舗ビジネス専門コンサルタントの高木悠が最速・最短で年商30億、店舗数30超を実現する実証されたノウハウをコンセプトにのれん分け制度構築、FC本部立ち上げ、立て直し、人事評価制度の整備など飲食店、整体院、美容院などの様々なビジネスの多店舗展開を加速させるために重要なことを対談形式で分かりやすくお話しする番組です。
田村:こんにちは。パーソナリティーの田村陽太です。配信第67回目となりました。本番組のメインパーソナリティーをご紹介します。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木悠さんです。よろしくお願いします。
高木:よろしくお願いいたします。
田村:高木さん、今日も頑張っていきましょう。
高木:はい、お願いします。
田村:本日の質問は、こちらとなっております。「整体院を2店舗経営しています。今後、30店舗展開を目標にしています。多店舗化に成功している企業の特徴を教えてください。」ということなのですが、これはすごい野望ですね。
高木:いやあ、いいじゃないですか。30店舗って夢がありますね。
田村:血気盛んな感じの経営者ですね、これは。
高木:こういう経営者をどんどん応援していきたいですね。
田村:いろいろ企業さんを見てこられたかと思いますけれども、どうでしょうか、多店舗化に成功している企業の特徴を教えていただけたらと思います。
高木:これをやったら成功するって言えないと思うのですが、ただ結構面白いことがあります。僕たちセミナーをやっているじゃないですか。のれん分けのセミナーとか、フランチャイズ展開のやり方をお伝えするセミナーをやっているのですよ。
田村:はい。
高木:そこに参加する企業って基本的には事業が成長していて、それで人材の問題を抱えていたりとか、もしくはフランチャイズ展開をして、より事業を拡大していきたいみたいな企業が多いんですよ。
田村:なるほど。
高木:だからもうビジネスとしてはうまくいっていて、これをどう拡大させていくかみたいな事で悩んでいる社長って多いのですよね。うちの会社に相談に来る会社っていうのはそういうところばっかりじゃなくて、1店舗とか2店舗を経営しているんだけど、やっぱり売り上げがなかなかうまく伸びないみたいな会社もあるわけですよ。
田村:はい。
高木:そういう方々と接している中で、セミナーに来られる方ってうまくいっているわけじゃないですか。その方たちと、そもそも売り上げが伸びないって悩んでいる会社、これにはもう明確に違う点が一つあるのに気がついたのですよ。
田村:さすがですね、高木さん。それは何でしょうか?
高木:その違いがシンプルなのですが、事業がうまくいっている会社っていうのは、必ず経営計画発表会みたいな場を設けているっていう事です。これは明確に違うのですよ。うまくいっている会社というか、拡大志向ということで相談に来る会社っていうのは明確な経営計画をまず持っていて、それでそれを全従業員さんに共有する場っていうのを、年に1回とか半年に1回位はやっているんですよね。
田村:はい。
高木:うちのセミナーに来た方にお話聞くと、7割とか8割位の確率でやっているのですよ。
田村:すごいですね。
高木:だけど売り上げで困っている会社とかそもそも二、三店舗位でつまずいている会社のお話を聞くじゃないですか。「経営計画発表会とかやっているのですか?」って聞くと、ほぼやってないのですよ。
田村:やってないですか!
高木:これは会社の規模とかじゃないのですよね。2店舗3店舗ぐらいでもそのセミナーに来た方に聞くと結構な確率でやっているのですよ。だからこれから30店舗展開を目指していくにあたって、こういう経営計画発表会みたいのをやっているかどうかっていうのは一つ大きな違いになるのではないかなと思いますね。
田村:なるほど。ちょっと素人で申し訳ないのですけど、経営計画発表会っていうのは、どういうプログラムで皆さんやられているのですか。
高木:いろいろあるのでしょうけど、結局計画発表会の目的って何かって言ったら、会社の明確な方向性、つまり今後どういう方向性に進んでいくかっていうのをちゃんと示していくとともに、会社が進んでいった結果、従業員さんがどうなっていくのかみたいな、従業員さんの幸せみたいなものも見えるようにして、会社と従業員さんの進むべき道っていうのを一体化させるわけですよ。
田村:はい。
高木:そういう観点から考えていくと、まず最初に会社が目指す姿やそれを実現した結果、従業員さんがどうなるかっていう従業員さんが得られる姿みたいなことをちゃんと提示して、それを実現するために解決しなきゃいけないような問題とか課題ってあるわけじゃないですか。
田村:はい。
高木:それを明確に示すのです。でも大体問題とか課題ってふんわりしているのですよね。抽象的な表現になるというか。例えば安定的に人材を採用できるような状況を作るようにしていかなきゃいけないとかですね。
田村:ふんわりしていますね。
高木:それを実現するために何するのですかっていう話で、具体的な取り組みが出てくるわけじゃないですか。そこが従業員さんの役割でもあるのですね。そういったものを示していくような感じですよ。
田村:そういうのが、プログラムの内容っていう感じなのですね。皆さん、企業がやられているのは。
高木:一般的な会社ではそんな感じですね。
田村:なるほど。ありがとうございます。ちょっと1個質問したいんですけども、経営計画発表会って言って、従業員さんをみんな集めて、「会社で頑張っていくぞ!」という感じでやるじゃないですか。そうすることによって、会社としてはそれが義務みたいな感じで、もうやらなきゃ、従業員さんから総スカン食らうみたいな事ってあるじゃないですか。
高木:はい。
田村:それって結構、企業としてはリスクになるのかなと僕は思ったりしたんですけど、それはどう乗り越えていったらいいとかってあるんですか。
高木:だからリスクになると思うんですよね、当然。だけど、目標とか計画がなかったとするじゃないですか。例えば最近だと箱根駅伝とかがあったわけじゃないですか。
田村:やっていましたね。
高木:みんな箱根駅伝で優勝したいとか、シード権取るとかっていう目標があるわけじゃないですか。それで目標とかがない状態で、あそこに出られます?という話なわけですよね。
田村:あれは相当な大変なトーナメントを勝ち抜いた方がやっていますよね。
高木:そうそう。優勝を目指すとか、シード権を目指すって言うことにはリスクがあるわけじゃないですか。できなかったらどうするの?みたいな。だけど全然そうなっていないですよね。
田村:はい。
高木:それは明確にそこを目標として示して、そこに到達するための何かカリキュラム的なものがあると思うのですよ。それで監督も選手も一生懸命やるわけじゃないですか。この結果行くか行かないかっていうのは神のみぞ知るんですけど、行かなかったら総スカンになるかと言ったらそうじゃないですよねっていう話です。
田村:なるほど。
高木:もし総スカンになるのだとしたら、多分経営者の伝え方とかの本気度が足りなくて、多分一体感作れていないんじゃないかという話なわけですよ。そういう観点で考えたら、むしろない方がリスクじゃないですかっていう話ですよね。
田村:今高木さんの話を聞いていたら、発表会の目標を絶対達成するぞって伝えるのじゃなくて、一緒に頑張っていくぞ!みたいな感じで発表会やるみたいなイメージですね。
高木:そうそう。会社の場合はまずその会社がどうなるっていう方向性を明確に示すじゃないですか。その結果従業員さんの幸せもあるのだっていうことをまずちゃんと確認しなきゃいけないですね。
田村:はい。
高木:そこがスタートで、それを実現するためには「これとこれとこれ」をやらなきゃいけないんだよっていうことが伝われば、従業員さんもそこに対してやる気になるじゃないですか。明確に共有できればという事です。そこをちゃんと共有して、会社と従業員さんが同じ方向性向いて、それでやるべきことがさらに明確になって共有されているから、確実に進んでいくわけですね。
田村:なるほど。意思統一を図っていくみたいな感じですよね。
高木:そうそう。意思統一を図るっていうところが最終的には経営計画発表会でなされるわけじゃないですか。だけど僕は思うのですが、計画発表会をやるからには適当にできないじゃないですか。
田村:そうですね。
高木:だから準備しますよね。
田村:どんな準備をするんですか。
高木:そこで発表する内容をちゃんと作っていかなきゃいけないじゃないですか。僕なんかが経営計画発表会ってどうやってやったらいいんですか?と聞かれた時に答えるのは、例えば何故こっちの方向に行かなきゃいけないんだとか、そのために具体的にどういうことをするのかみたいな話っていうのは、やっぱり相当の納得感がなければいけないと思うんですよ。
田村:はい。
高木:「何でそうなの?」みたいな感じで、従業員の方に「?」が出ちゃったら、実行度なんて上がりようがないわけですよね。だからそれを、ちゃんと考えていかなきゃいけないわけじゃないですか。
田村:それって考えるのがめちゃくちゃ難しくないですか、論理的に考えたりとかって。
高木:でも本来会社が進むべき方向性っていろんな外部環境の状況や、会社が持っている強みとかがあるわけじゃないですか。そういうのを整理して、こういう方向に進むべきだっていう風に考えるっていうのが、「べき」論じゃないですか。
田村:はい。
高木:経営計画発表会をやるとだからそれを考えざるを得ないのですよ。だって紙に書いたりしなきゃいけないじゃないですか。紙に書けないっていうことはあやふやな状態だからそれを研ぎ澄ましていくわけですよ。
田村:確かに。
高木:そういう過程を乗り越えた上でやっているわけですから、それは方針も明確だし、明確な方針が従業員に共有される場があるからそれは実行度も上がりますよね。だけど経営計画発表会がないっていうことは、こんなリスクがあります。経営計画が明確に持っていればまだいいと思うんですよ。でも、発表する場がないっていうことは別に計画を作っても作らなくても死ぬわけじゃないんで、だから作らない可能性高いじゃないですか。
田村:そうですね。
高木:だからあとはもう確率論で作っている会社っていうのは結構伸びているし、作らない会社で共有していない会社っていうのは、要は伸びにくい。明確な自分たちの問題点とか理想とかが明らかになっていないからじゃないですか。
田村:確かにそうですね。
高木:そうなんじゃないかなって僕は分析しているんですが。
田村:確かにそれはありますよね。高木さんの話を聞いて思ったんですけど、こういうポッドキャストとかも音声を世に発信するってことをすると、自分もどういう原稿で喋ろうって、原稿をやっぱり作ったりするんですよね。紙に落としたりするんですよね。それもやっぱり発表会と一緒で、何か発表するってなったら、何か紙で作らなきゃみたいな話になって行動しますもんね。
高木:そうそう。アウトプットをしないと明確になっていかないと思うんですよ。そういう意味では経営計画って大事ですよね。しかも緊張感があるというのもいいですよね。だってさっきリスクがあるのでは?と田村さんがおっしゃった通りですけど、まさしく従業員さんに言って、到達しなかったっていう姿はあんまり従業員さんに見せたくないじゃないですか。
田村:そうですね。
高木:じゃあ見せなかったらどうなりますか?と言ったら、見せなかったらやらないっていう話になりやすいわけですよね。出しちゃったらやらなきゃいけないわけじゃないですか。
田村:やるしかないですよね。
高木:社長にも緊張感が生まれますよね。それぐらいの方がいいんじゃないですか。
田村:適度な緊張感を持ちながら、経営について従業員さんと考えていく場、これはすごく大事だなって思いますよね。
高木:僕なんかよく「健全な強制力」と言っているんですけど、それなのですよ。
田村:難しい言葉ですね。それは何ですか?
高木:だから人って基本的に、楽な方に流されていくわけじゃないですか。だから、やるきっかけみたいなものを自分で自ら作っておかないと、なかなかやらないと思うのですよ。経営計画発表会をやりますって従業員さんに年に1回やりますって言うじゃないですか。
田村:はい。
高木:そうするとやらないわけにはいかなくなりますよね。そこにだから健全な強制力が働くと思うんですよ。だからやんなきゃいけないって。
田村:そういった意味での「健全」なんですね。
高木:そうそう。だからそれを自分で自分に健全な強制力を課しておけば、行動って進むのですよ。そういうのはやっぱり意図的に作っていった方がいいと思いますよ。
田村:人生適度なプレッシャーがあった方が、生きがいがやっぱり生まれたりしますからね。
高木:そうそう。でないとやらないでしょっていう事です。
田村:やらないですね(笑)
高木:そうそう(笑)
田村:なるほど。ありがとうございます。結構時間が近づいてきたんですけども1個だけ質問してもいいですか。経営計画発表会っていうと僕すごい大それたイメージがあって、例えば株主総会的な発表会の場を作らなきゃいけないのかなっていう気がするんですけど、そういうものなのですか?
例えば中小企業とかでも、会議室とかあるじゃないですか。会社の中の小さい会議室とかで発表会するやつで従業員さんが本当にモチベーション高くできるのかなと思っていて、つまり経営計画発表会の場作りっていうか、どういう場所だったらいいのかとかってあるんですか。
高木:良い質問じゃないですか。これは会議室とかでもいいんですよ。とりあえず僕がおすすめしているのは、「非日常的な場を作る」っていうことを推奨しています。
田村:それは何ですか?
高木:例えば普段会議室で会議やるじゃないですか。例えばそしたら年に1回ぐらいやる経営計画共有会とか発表会っていうのは、例えばホテルでやるとか、普段やらないような環境に身を置いてやるわけですよ。これによって何が生まれるかっていうと、当然経営者に緊張感も生まれるんですけど、やっぱり従業員さん側の姿勢は変わりますよね。
田村;なるほど。
高木:伝わるじゃないですか、その会社の本気度みたいなのが。
田村:そうですね。
高木:だから年に1回とか半年に1回ぐらいやったら意図的にそういう場を変えて、本気度をちょっと上げてやるのがおすすめですし、意外とうまくやっている会社っていうのはそういうところで大々的にやっているケースが多いですよ。
田村:ホテルの「何とかの間」みたいな所や、結構大きい会議室を使ってやっていくみたいなイメージですか。
高木;人数がいっぱいいるんだったらそういうところでも良いでしょうし、ホテルにも小さい会議室とかもいっぱいあったりするじゃないですか。
田村:ありますよね。
高木:わざわざああいうところに行ってやって、その後ホテルで食事して懇親するとかそんな感じでいいんじゃないですか。
田村:なるほど。さっきの非日常な空間で、従業員さんと一緒に経営計画発表会をするっていうのはすごく大事ですね。
高木:そういうことをやっていくと結構意識が変わってくるんですよね。
田村:わかりました。ありがとうございます。本日は多店舗化に成功している企業の特徴ということでお話させていただきました。ありがとうございました。
高木:ありがとうございました。
無料メルマガ登録
専門コラムの他、各種ご案内をお届け中です。ぜひ、ご登録ください。

セミナーのご案内
店舗ビジネスの多店舗展開やのれん分け・FCシステム構築を進めていくため、具体的にどう取り組んでいけばいいのか、どのような点に留意すべきか等を分かりやすく解説する実務セミナーを開催しています。
セミナー一覧ぺージへ