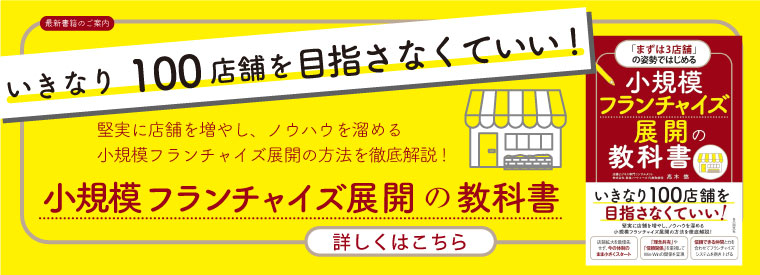当社で働く社員に明るい未来を示したいため、のれん分け制度を導入するつもりです。
できる限り独立のリスクを抑制したモデルにしたいのですが、タカキさんはこの点についてどう思いますか?
これは、先日のれん分け制度構築のことで弊社に相談に訪れた整骨院7店舗を営む経営者からいただいたご相談です。
ご相談者はとてもスタッフ想いの方で、「スタッフのリスクをゼロにして独立を応援したい」とのことでした。
このような考えは、スタッフの人生に大きな影響を与えるのれん分け制度を導入する経営者のマインドとしては、あるべき姿といえると思います。
一方で、スタッフの側によりすぎたのれん分け制度を設計しているケースでは、経営者が理想としている姿を実現できないことも少なくありません。
そこで、今回は社員の独立リスクを抑制したのれん分け制度を設計する際の注意点について考えてみたいと思います。
(1)のれん分け制度を利用するスタッフの特徴
のれん分け制度を設計していくにあたり、のれん分け制度を利用するスタッフの特徴を理解しておく必要があります。
経営者の中には、のれん分け制度の利用者は「独立志向の高い人材」と考えている方もいるかもしれません。しかし、このような人材は、意外にものれん分け制度の利用対象者にはならないことが多いです。
その理由は、独立志向が高い人材は、のれん分けを利用せず、独力で独立をしてしまう傾向があるからです。
のれん分けを提案しても、それを受けず自力で開業してしまうケースがあるのは、たいていの場合が、独立志向の高い人材にのれん分けを利用してもらおうとしているからです。
一方で、独立志向がある人材の中には、「独立したいけれども、あと一歩が踏み出せない」という層が一定割合存在するはずです。
このような層は、会社が積極的に独立をサポートすることで、独立に向けた一歩を踏み出す可能性があります。
ですので、のれん分け制度を設計するにあたっては、「独立したいけれども、あと一歩が踏み出せない」層を念頭に、その一歩を踏み出す仕組みを整備していくことが前提となります。
この観点から考えれば、前述の経営者の相談にある「できる限り独立のリスクを抑制したモデル」という考えは、のれん分けによる独立者を輩出するうえで理にかなっているといえるでしょう。
(2)独立者のリスクを抑制するということは、その分本部がリスクを負う仕組みである
ただし、ここで注意しなければならない点があります。
それは、独立者のリスクを抑制するということは、抑制したリスクを本部が負うことになるという点です。
例えば、独立者のリスクを抑制するために、
・本部が店舗をつくってあげて、独立者の自己資金はゼロでOK
・本部が働くスタッフを雇用して貸し出すので、雇用の心配無し
・売上が低くて赤字の場合には、最低減の給料を保証
といった仕組みを整備したとします。
独立者から見れば全くリスクがないため、とても魅力的な仕組みに見えるでしょう。
しかし、のれん分け後に仮に経営が上手くいかなかった場合、本部は
・店舗の投資回収ができない。むしろ、撤退費用まで負担しなければならない
・店舗が撤退した場合、本部が人件費を負担しなければならない
・独立者の給料を保証した結果、本部は赤字垂れ流しになる
といった問題が生じることになります。
このように、独立者のリスクを抑制するということは、本部が代わりにリスクを負っているということでもあるのです。
この状態では、独立する者はよかったとしても、会社に残された社員は果たして幸せになれるのでしょうか。
本部としては、独立者のことだけではなく、会社に残るスタッフの幸せも考えておかなければなりません。
その観点から考えれば、独立者のためとはいえ、本部が独立者の代わりにすべてのリスクを負うような制度設計はするべきではないといえるのではないでしょうか。
(3)のれん分けは「独立させること」がゴールではない
また、のれん分け制度を導入する会社が心にとどめておかなければならないことがあります。
それは、「リスクを負わずに独立したとして、経営者になることができるか」という点です。
経営者と従業員の最大の違いは、背負っているリスクの違いにあります。
大きなリスクを背負っているからこそ、経営者は誰よりも会社のことを考え、行動するのではないでしょうか。
裏を返せば、リスクを背負っていなければ、たとえ肩書は経営者になったとしても、誰よりも会社のことを考え行動する真の経営者になる可能性は低いのです。
創業経営者と雇われ経営者との意識に大きな差があるのもこのことが要因でしょう。
経営をする以上、独立者には経営者としての覚悟を持ち、自立してもらう必要があります。
社員の幸せを思うのであれば、社員への恩返しという側面を大切にしつつも、一定程度のリスクを負わせることも必要でではないでしょうか。
のれん分け制度を導入する本部経営者としては、のれん分けは「独立させること」がゴールではないことを心にとどめておく必要があります。
まとめ
以上、今回は「社員の独立リスクを抑制したのれん分け制度を設計する際の注意点」について触れてみました。
「スタッフのために本部ができる限りのことをしてあげたい」という考えは、スタッフの人生に大きな影響を与えるのれん分け制度を導入する経営者のマインドとしては、あるべき姿といえます。
一方で、スタッフのために本部がなんでもかんでも面倒を見てしまうのでは、独立者が真の経営者になることができず、結果、経営が上手くいかない可能性が高まることになります。
社員への恩返しという側面を大切にしつつ、経営者として最低限のリスクは追ってもらう。
のれん分け制度を成功させるためには、このバランスをしっかりととることが重要なのではないでしょうか。
なお、のれん分け制度構築についてさらに詳しく知りたい方は、こちらのコラムも合わせてご覧ください。
無料資料ダウンロード
のれん分け・社員独立FC制度構築の手順やポイントをまとめた資料を無料進呈しています。宜しければ、下記よりダウンロードください。

セミナーのご案内
店舗ビジネスの多店舗展開やのれん分け・FCシステム構築を進めていくため、具体的にどう取り組んでいけばいいのか、どのような点に留意すべきか等を分かりやすく解説する実務セミナーを開催しています。
セミナー一覧ぺージへ